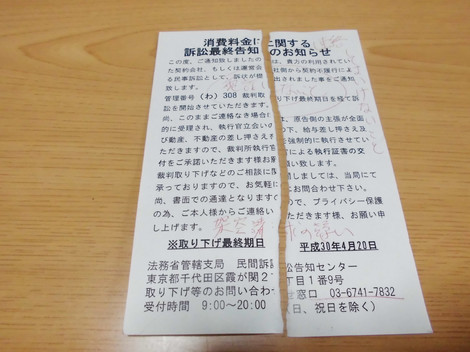サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: yeshangさん
2018/04/27 18:43:06
icon
朝鮮半島の南北対話について
何度も騙されてきて、その都度核開発・核実験、ミサイル発射が繰り返されてきました。
今度こそと思いますが、キーワードとなるのは、日本人拉致被害者が本当に解決されるかにかかっています。
日本人拉致被害者が解決されない限り、北朝鮮の本気度はないと考えます。
拉致被害者のことまで突き進めば、北朝鮮の本気度がうかがえます。
日本としても世界も、拉致被害者のことを大きな指標として(本気度を測る目安として)、今回の成り行きを見守るべきです。 -
from: yeshangさん
2018/04/18 22:05:05
-
from: 大塚のあゆさん
2018/04/18 15:19:30
-
from: 大塚のあゆさん
2018/04/14 21:59:10
-
from: yeshangさん
2018/04/12 22:37:52
icon
ベネズエラのインフレ率が8878%だと
中南米のベネズエラのインフレ率が年約90倍と今日の夕刊に出ていました。
100倍とすると、100円の缶コーヒーが1万円になる勘定です。
500円のコンビニ弁当が5万円に。
1千万円の貯蓄があっても10万円の価値になり、1ト月も生活できません。
30年近く前にブラジルに行く機会がありましたが、ここでもすごいインフレで、毎月30%のインフレ率、年間にすると3.6倍の物価高でした。
このため、銀行のクレジットカードで支払うよりは現金支払いだと売値の30%引きでした。1か月後に入る銀行の現金より今の現金のほうがよいとの考えでした。
外国はカード決済と考えていた友人はこれにはとまどっていました。
何しろカードだけで日本円やドルの現金をあまり持ってなく、市内では円・ドルが2倍ほどで現地通貨に換えられたからです。
日本も1000兆円もの国債を抱えていて、いつ何時ブラジルやベネズエラのようなハイパーインフレになるかを警告する本が昔から出ています。
100倍のハイパーインフレになると、政府の借金は1/100に目減りするので、実質10兆円になるので政府としてはうれしい限りですが、庶民はたまったものではありません。
政府・日銀の2%のインフレ期待どころではありません。 -
from: yeshangさん
2018/04/11 19:29:53
icon
来日した中国人の感想
何人かの中国人に、日本の印象を聞きました。
みんな、「日本は干浄だ(清潔)」と言いました。
中国は文化大革命のころ、ゴミもハエもいないと言われていましたが、そんなに清潔ではなく、食堂では食べかすが卓に山積みで、従業員も椅子を拭いた雑巾でテーブルを拭き、その真っ黒な雑巾も泥水のバケツで洗っているという始末でした。
観光日本を更に発展させるには、日本の清潔さ(街も食品もサービス、環境)、犯罪の少なさ、そして日本の様々な文化、自然を知って堪能してもらい、新たな日本各地へのリピーターを増やすのが大切と思っています。
少なくとも、干浄だ(清潔)という感覚は大切にしたいと思います。 -
from: himeさん
2018/04/08 11:35:38
-
from: yeshangさん
2018/04/04 19:28:38
icon
インフレのない経済成長を
政府・日銀は2%/年のインフレをしきりに唱えていますが、この低利息の世の中で物価だけが上がることはいかがなものかと思っています。
しかも最近の物価高は景気と関係のない輸入品によるもの(石油・食料品・原材料など)が主体で、日本の実体経済に寄与するものではありません。
このようなもので、物価が上がったと一喜一憂するのでなく、日本の実力で景気を引き上げる努力をしてほしいものです。
30年前に日本が技術協力していたシンガポールは、既に1人当たりGDPは日本の1.5倍になっています。
このまま、眠れる猫のような状態で眠り続けていていいのでしょうか。 -
from: yeshangさん
2018/04/03 20:57:56
icon
飲料に砂糖税 - アジアで拡大
今日(4/3)の日経新聞1面の記事です。
肥満につながる清涼飲料の増加に歯止めをかけ、医療財政の負担を軽減させるためとのことです。
1980年中ごろ中国北京で生活する機会がありましたが、女性はみんなすらっとしたやせ型で足も長くて細かったので、中国生活経験者の仲間でなぜだろうと議論になったことがあります。
食生活での、お茶を飲む習慣だろう、いや、ニンニクを多用しているからだと、いろいろありました。
しかし、原因は摂取カロリーの低いことと、砂糖の少なさのようでした。
当時は、中国国内で十分な食料が供給できず、肉や油は中国料理の基本と考えていますがそれも十分でなく、砂糖は貴重でした。
私が当時調べたところ中国人1人当たり砂糖消費量は極端に少なくて、日本人の戦前以前の状態でした。
このためか、当時おいしい料理は砂糖と油をしっかり使ったものと言われていました。1990年代以降中国の食糧自給率が改善され、所得の向上とともに、1人っ子政策もあり、若者や子供の肥満が目立つようになりました。
今は、都会ではダイエットのための運動や食品に人気があるそうです。
アジアで砂糖税が拡大していることは、アジアで所得が拡大し、砂糖需要が高まった結果だと考えています。所得の増加がアジアで拡大している結果でしょう。
ちなみに、日本では1980年代以降1人当たり砂糖消費量は頭打ちになっています。
日本でも糖質の取りすぎに警告する記事や新聞広告がありますが、スボーツをしたり読書や研究にいそしむ人には糖類・砂糖・ブドウ糖は必要です。
私は、糖尿病なのでインシュリン注射をしていますが、空手道の最中や読書後に血糖値の低下を覚え砂糖やブドウ糖をよく飲むことがあります。
それでも血糖値は低いままのことがありますので、適度な糖質・佐藤の接種は必要と考えています。