サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: 一久さん
2006/02/17 20:09:21
icon
武部メール疑惑
【武部疑惑について】こういう疑惑が持ち出されると、身に覚えがなくとも慎重な返答をするのが普通であろう。けれども、武部氏も小泉首相も(小泉氏は普段から考
【武部疑惑について】
こういう疑惑が持ち出されると、身に覚えがなくとも慎重な返答をするのが普通であろう。けれども、武部氏も小泉首相も(小泉氏は普段から考えなしのことが多いが)、拙速ともいえるコメントを出した。もしも、疑惑が事実であったならば、言い逃れが困難になるような反論をしている。さらに、自民党としても、民主党の永田寿康氏に対する懲罰動議を検討しているという。
こうなってくると、自民党のほうではすでに、疑惑メールの内容に信憑性がないということを突き止めたのではないか、と思えてきてしまう。
民主党側としては、立証十分な証拠を掴んでおり、その上で「遠山の金さん」みたいに最後に悪人を一網打尽にすべくその時を待っているのかもしれない。ゆえに自民党側にこのような反応が起こったことを歓迎しているのかも。
どちらにしても、引くに引けない状況になったようだ。
それにしても、マスコミのオチャラカぶりには、毎度のことながら驚かされてしまう。今朝の某番組では、「文面をみるかぎり、ホリエモンの文にみえる」「なかなか文体はマネできない」とか言う作家(?)氏が登場していた。このコメントには、本当にイスから転がり落ちそうになってしまった。誰かに成り済まして小説を書けと言われたら確かに困難だろうが、こんなメールを「ホリエモンらしく」作るぐらい、小学生でもできるだろう。 (^ー^)-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 9
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

from: S1さん
2006/03/04 06:29:17
icon
「Re:Re:Re:とんでも八分、歩いて十分♪」>でも、その前日の報道には、塗りつぶされていないのを永田氏から見せられたとかいう別の議員がテレビに出て
-
-
from: 一久さん
2006/02/28 13:27:05
icon
ハンナ・アーレント 全体主義の起原 「全体主義」
ふたたび、「全体主義」を借りてきました。厳密には、同じ本ではないようだ。以前借りたものは、ハードカバーだったが、今回は並製版となっている。このまえのと
ふたたび、「全体主義」を借りてきました。厳密には、同じ本ではないようだ。以前借りたものは、ハードカバーだったが、今回は並製版となっている。このまえのとくは、「反ユダヤ主義」だけが「並」だった。
三月いっぱいで、「全体主義の起原」についての感想をまとめていきたい。
追伸:
次回、4月〜6月期の課題図書は、以前予告したとおり、「リヴァイアサン」ホッブス著です。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/28 13:19:04
icon
民主党HPに激論掲示板を作れ
【民主党掲示板を】議員達が意見を闘わせる公開の場所としては、インターネットの掲示板を民主党のWEBに作ることが最も簡単でかつ効果的である。ただの掲示板
【民主党掲示板を】
議員達が意見を闘わせる公開の場所としては、インターネットの掲示板を民主党のWEBに作ることが最も簡単でかつ効果的である。ただの掲示板ではない。民主党の国会議員だけが書き込むことのできる掲示板である。この掲示板での意見や批判は、法に触れない限り自由とする「掲示板での批判は自由である、されど国会での党議拘束には服従せよ」ということだ。
また、国会議員全員に、この掲示板への書き込み義務を課す。一カ月に10本の論文(エッセー)の掲載を義務づける。小沢氏も、管氏も、鳩山氏も、例外ではない。彼らの論文見たさに、この掲示板へのアクセス数は、急激に増えるであろう。
それによって、他の有名でない議員の意見も、国民に読んでもらえるようになる。そんな掲示板があれば、張りきらない新人議員がいるであろうか。また、少数意見派に属する者も、大いに熱弁をふるって自己の意見を述べるであろう。そのような場所を提供してくれる政党から、なんで出て行くものであろうか。
民主党の百人を越す国会議員が、月間一人10本の書き込みをする。合わせて、千本以上となる。一日平均で30本を越す。しかも、2ちゃんねるなどとは違って、全員が国会議員という責任ある立場の人間が、身分を明らかにして書いた署名記事である。この掲示板は、誕生した瞬間に、日本一の政治関係の掲示板になるだろう。
【下部リーグ掲示板をつくれ】
さらに、この「メジャーリーグ」とは別に、その下部リーグとして、一般人も書き込める掲示板をつくれば、党員獲得の助けになろう。下部リーグは、党員だけが書き込める掲示板、参加登録をした者なら党員以外でも書き込める場所、等に分けてもよい。あるいは、熱心な参加者だけを選抜(国会議員推薦により)して参加できるようにした掲示板などがあってもよい。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/28 13:17:36
icon
寄り合い所帯の民主党
【激論して結束固まる】民主党が寄り合い所帯である、ということは誰でも知っている。党の意見をまとめ、統一した見解を出せるようにしなければ、到底、自民党と
【激論して結束固まる】
民主党が寄り合い所帯である、ということは誰でも知っている。党の意見をまとめ、統一した見解を出せるようにしなければ、到底、自民党と互角に戦えないということも、皆が分かっている。しかし、にも関わらず、それができない。できるようになる兆しすらない。そうなってしまう理由は、意見を取りまとめようとすれば、不満のある人間が出て行ってしまう、党が分裂してしまうという危機感にある、ということもまた、言わずとも知れたことである。
では、どうにもならないのか。民主党は「生まれた時、すでに死んでいた」のだろうか。
民主党を蝕んでいるこの宿病の根本原因は、「意見が噛み合わねば分裂する」という迷信を信じていることにこそある。「雨振って地固まる」「ケンカするほど仲が良い」「バトルした相手のほうが、知らない相手よりも協力してくれる」等々、昔からいうように、激論し、意見を闘わせたほうが、むしろ党内の結束は固まる。
分裂する、とか、離反者が出る、とかいうのは杞憂である。なぜならば、自分の意見が少数派に属する者にとっても、その意見を発表し、討論する場所は、「大きな場所」のほうが良いからである。小政党の中で多数派に属するよりも、たとえ百戦百敗であっても、大政党の仲に自分の意見を主張する場所を得たほうが、世間にアピールできるからである。
そう、党議拘束に反する意見を持つ党員にとって、それでも党に残ることを選択させる要素とは、「世間にアピールできる」装置がその政党にあるかどうか、ということなのだ。これさえあれば、党を出て行く者は多くはない。逆に、このようなシステムが無ければ、ちょっとした意見の違いで離脱する者が出て来るだろう。
具体的な例でいえば、憲法第九条の改正に反対する党員がいたとして、彼が民主党内部で反対論を述べて他の党員と激論する様子が公の場に提供されるのであれば、結果として彼の主張が敗れ、民主党の政策として憲法改正が選択されたとしても、彼はもって瞑するであろう。逆に、そのような場を与えられず、野党に在籍したほうが論戦の場に出てこれるのであれば、彼は離党の誘惑を常に感じることになる。
大事なことは、違った意見のぶつかり合いを、その激論のさまを公開して、議員たちが自分の意見を国民にアピールできる場所を作るということである。そのような場所を党が用意できるのであれば、所属議員たちは、決して軽々に党籍を離れたりはしない。
激論を公開せよ。さすれば、皆、結束する。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/25 21:05:50
icon
錯乱しているのか民主党
錯乱しているのは、民主党全体ではないのだろうか。金の流れが問題であって、メールの真贋が重要ではないのだ、とか言い出す始末だし。こんな子供だましの言い分
錯乱しているのは、民主党全体ではないのだろうか。
金の流れが問題であって、メールの真贋が重要ではないのだ、とか言い出す始末だし。こんな子供だましの言い分で、国民を欺けるとでも思っているのだろうか。
証拠があってこそ、「金の流れを追求」できるのであって、証拠の信憑性がなくなれば、追求できなくなるではないか。証拠に信憑性がないのに追求する、というのはムチャクチャである。
早い話、亀井静氏がナガタ氏に金を渡して、武部を貶めようとしたのだ、その金の流れを追求することが先決だ、と言ってもいいことになってしまうではないか。
もちろん、こんなネタは、まったくのフィクションである。しかし、証拠も示さずに追求することが許されるのであれば、これもアリではないか。こういうのを、恐怖政治というのだ。
つまり、民主党は、恐怖政治をやる、と言っているのである。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/21 21:37:12
icon
一円玉問答
【雑談・一円玉問答】一円を拾うのに消費するエネルギー・コストは、一円以上だとかいう。では、拾うべきではないのだろうか。結論からいうと、拾ったほうが得だ
【雑談・一円玉問答】
一円を拾うのに消費するエネルギー・コストは、一円以上だとかいう。では、拾うべきではないのだろうか。結論からいうと、拾ったほうが得だと思う。理由は、「蓄える」ことができるからだ。
運動に使うカロリーは、蓄えることができない。いや、できない訳ではないが、それは体脂肪という名前の、ありがたくない貯蓄として蓄えられることになる。これに対して、一円玉というもの、貨幣というものは、蓄えることができる。拾うのに使ったコストが一円をオーバーしたとしても、そのオーバーした部分は、ため込む為の変換コストであると解釈すべきものだろう。充電池に電気を貯める時、やはり損失が生まれている。それと同じである。
そういえば以前、太陽光線を当れば水素を出すとかいう金属(?)の研究成果が報道されていた。それに関して、どこかの掲示板に書かれていた意見には、あまり高い評価をするものが少なかった。いわく、太陽電池のほうが効率がいい、とか、石油成分の採れる植物を栽培する方式のほうがいいのではないかとか。
しかし、「蓄える」というキーワードを使って、これを考えると、この新技術は捨てたものではないといえるだろう。太陽電池のほうが、現時点では効率がいいとしても、電気というものは、貯めることが難しい。電池に貯め込む場合、当然、ロスがでる。電気分解で水素を作って貯蔵するという方式でも、やはり損失がでる。水素方式にはそういうロスがない。
石油成分は、水素よりも貯蔵が容易である。だが、植物から採る方式は、エネルギー効率が悪いのではないだろうか。いや、効率そのものを無視しているようだ。植物が太陽から得た総エネルギーと、得られた石油成分のエネルギーとを計算して、効率を記した記載はそこには無かった。植物が日中ずっと、何日間も太陽からの光を得ていることを考えれば、その入射エネルギーは膨大なものになるはずであり、結果的に効率をすこぶる小さくしているはずである。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/18 21:21:44
icon
IT革命とはなにか
【IT革命とはなにか】19世紀産業革命の定義として唯一たしかなものは、それが生活物資の飛躍的な量的増大であったということである。同じように、今現在進行
【IT革命とはなにか】
19世紀産業革命の定義として唯一たしかなものは、それが生活物資の飛躍的な量的増大であったということである。同じように、今現在進行中のIT革命の定義として唯一たしかなものは、それが飛躍的な情報量の(その記憶量と通信量の)増大であるということである。双方向性がどうとかいう話は、末子枝葉のことにすぎない。
IT革命によって、情報量が増大する。そのことの意味を、はたしてマスコミもIT起業も、十分に理解しているであろうか。政治家や官僚が理解していないのは止むを得ないことだとしても。
情報量が増大するということは、それまで情報網から弾き出されていた情報が、その存在する場所を与えられるということである。これまでの情報網においては、伝達容量の限界から、情報網に載せることのできるものとできないものを峻別しなければならなかった。そのような足枷がなくなったということを、これは意味するのである。
【具体例】
「小学校からやりなおせ」という言葉は、いままでは単なる罵倒語でしかなかった。しかし、ハードディスクの容量が100ギガバイトに達する今日、ノートパソコンの中に全教科・全学年の教科書を記憶させておくことは容易である。ゆえに、IT革命の後は、この言葉は中高生を罵倒する言葉ではなくなり、実際に小学校のテキストを呼び出して勉強しなおすことを可能にする。小中高校での教育において「一人一代のパソコン」導入が望ましい理由は、ここにある。
もうひとつ、教育関係で例をだそう。
参考書や問題集を作る者にとって、最大の課題は、どれぐらいの解答・解説を添付するかということである。詳しくすればするほど、分かり易い本にすることができるが、すべての問題についてそれをすれば膨大なページ数になってしまう。問題数を削るか、解説を省略するかで、常に葛藤せざるを得ない。
ところが、DVDの大記憶容量やネット接続による無限大と言ってもいい記憶容量が使えれば、この問題は解消される。書物一冊の容量は、普通、1MB以下である。1GBあれば1000冊の書物に匹敵する解説を載せることができる。1000問の問題それぞれに対して、書物一冊分の解説を施すことができるのである。HDにプリインストールする場合や、ネット接続の場合は、さらにすごいことになる。
教育以外でも、同様のことができるようになる。要は、いままで片隅に押しやられていた情報は、少ない情報しか載せる場所を与えられていなかったが、革命後の世界では、片隅に「情報の大陸」があっても構わない、ということなのである。
アイドル情報でいえば、ネット社会においても芸能プロやTV番組のHPでの紹介には、有名アイドルがデカデカと載る。この点までは今までと変わらない。だが、片隅の新人アイドルに与えられた紹介欄の大きさが違ってくる。IT革命後においては、どんなに小さな名前しかトップページに載っていないアイドルであっても、そこをクリックしさえすれば、その新人についての膨大な情報が表示されるのである。その新人アイドルの身内や後援会のHPと繋げ、さらに大きな情報源を提供することもできる。
「片隅のもの」に膨大な紹介欄を与えることができる。それがIT革命である。ところがネット上の通信販売HPなどを見ていると、旧来のチラシ広告の旧癖から抜け出せていないものがほとんどではないか。売れない商品は、相変わらず、片隅に載るくらいの情報しか表示されない状況におかれている。「チラシの癖」が染みついているのである。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/14 22:01:20
icon
mixi とイジメの構図
「MIXI」と「イジメの構図」【「MIXI」というものがあるらしい】すでにMIXIを使っている人からの招待を受けた者だけが会員になれる、閉鎖的(?)な
「MIXI」と「イジメの構図」
【「MIXI」というものがあるらしい】
すでにMIXIを使っている人からの招待を受けた者だけが会員になれる、閉鎖的(?)なネットサービスであるらしい。内容は大雑把にいって、mixi以外と変わりないようだが。
「招待されないと参加できない」という制約を付けることで、「2ちゃんねる」的な騒動を回避できるとかで、今日(2/14)の産経新聞大阪版夕刊などにも紹介記事がでていた。すでに会員が300万人を突破したとか。
【心の違和感を感じる】
「招待が必要」という制約を目の前にして、ふたつの感情が沸いて来る。ひとつは、「お高くとまりやがって」、という反発であり、もうひとつは、「参加者になってみたい」という願望である。しかし、それらと同時に、なぜか奇妙な違和感、いや、既視感を感じる。なにかイヤな臭いを感じてしまう。なんだろうか、これは。
制約を設けることによって、参加者やその言動の「質」を保とうとする姿勢は、それなりに評価できる。それは解らないことはないのだが、なにかがおかしい。
おかしな感じのひとつは、「300万人」という数字に対する「恐怖」感であろう。これが、数千人規模であれば、こんな感じは受けない。三百万人にも達するのに自分は、という疎外感である。
もうひとつは、「招待」という形式に対する疑問である。「参加申し込み形式」と違って、他人による評価(しかもそれはまったくの主観による評価である)、他人の勝手な解釈によって自分が参加できるかどうか決まってしまうという非主体性の問題である。
しかし、主観であるが故にその「評価」は全人格的なものとなり、「三百万人も招待されているのに」招待されないでいる自分は、その全人格を誰にも認められていないのではないかという焦燥感を生む。
「他人の主観による評価」「主観で自分の人格が決められる」「300万人の側ではない自分」この三つがないまぜになって、この奇妙な違和感を創り出している。
【脱線】
例えば、昔のパソコン通信と比較すれば、よく分かる。パソコン通信もまた、閉鎖的なサービスではあったが、会員になるには、自分で申し込みをするだけでよかった、その入会審査は社会的な基礎事項を満たしているかどうかという客観的なものであったし、それゆえに人格的な評価とは無縁のものであった。当然、なんの恐怖も焦燥感もありはしない。
:閑話休題、 脱線前にもどろう:
【どこかでみたような】
この構図、しかしどこかで見たような気がする。
集団の一部もしくは全部が、他人をその主観で評価し、否定的評価をうけた人間は全人格的に阻害される。しかし、その評価は主観にたよっているので、いつ誰が「被害者」の側にまわるか分からない。ゆえにそうならないように、「評価される側」ではなく「評価する側」へ入り込みたい、否、入り込まなければいつ阻害されるか分からないという恐怖を皆が持っている社会。
これは、まさに「イジメの構図」ではないか。「なんということだ、これは!」
「mixi」と「イジメ」とは、同じ社会的モデルを持っているのである。奇妙な違和感の正体は、イジメの構図に対する拒絶反応だったのだ。
ここで一句、「招待の/正体みたり/イジメかな」 一久-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 一久さん
2006/02/11 21:09:46
icon
官僚病について
図書館で考える官僚についての考察例えば私が近所の小さな図書館に、大塚久雄著作集を古本屋から買って寄贈しようとしたとする。ただし、私には条件がある。この
図書館で考える
官僚についての考察
例えば私が近所の小さな図書館に、大塚久雄著作集を古本屋から買って寄贈しようとしたとする。ただし、私には条件がある。この本は貴重なものなので、市の中央図書館に持っていかれる恐れがある。また、収蔵された図書館でも、開架されずに書庫に保管される危険がある。事実、大阪市と大阪府の中央図書館に収蔵されているものは、どちらも書庫に死蔵されている。これでは、「だれにでも分るように」と、この著作集を編むときに大塚氏がわざわざ書き直した努力が無駄になる。「だれにでも」触れることのできる状態にはないのであるから。
そこで私は条件を付ける。この小さな図書館から動かさないこと。開架棚におき、貸し出しできるようにすること。このふたつである。ところが、図書館の係員は、図書館に置く図書の選定は図書館でやるので、寄贈された図書がどうなるかは保証できない、というの
である。これではまったく、お話にならない。
この図書館の決まりによって、古本屋は私に本を売ることができず、市民はこの本に触れることができないことになる。 誰もが損をすることになるのである。
さて、大塚久雄著作集ほどの文献を、もしも読書家であったならば寄贈されることを欲しない訳はない。だが、図書館の役人にそういう意識を期待できるかどうか。そもそも、この小さな図書館が住民の為になるように運営されるには、図書館の役人が運営するということそれ自体に無理があるのではないだろうか。
もしも図書館のサービスを向上していこうという意識があったならば、寄贈された図書の行方は役所にまかせろ、などと言うはずはない。慎重に選定のうえで、受け入れるかどうか決定してからお預かりするというのが筋であるはずだ。
そうでないのはなぜか?
それは、図書館員が寄贈を受ける、本を選ぶということに、なんらの精神的作業も要求されていないから、である。精神的作業とは、ここでは住民に良い書物に触れる機会を与えたいという意志であり、そのために本を選ぶ行為である。
そういうものがカケラほどもあれば、寄贈を申し出る者に対して、最低限度の誠意を示すはずであるが、まったくないのであれば、寄贈品は単にゴミと同じ扱いを受けることになる。
ここに官僚制の本質がある。つまり、官僚にとって精神的作業というものは本来、彼らの業務ではないのである。図書館の係員の例で言えば、彼らの仕事は貸し出しや返却を滞りなく行なうことであり、図書をキチンと整頓することである。住民によい本を、とかいうことは、本来、彼らの仕事ではない。
そういう判断は、もっと別の人々、実務者とは別の、住民サービスの改善を目的とする指導者が別に置かれねばならないのである。いわば、業務改善担当者である。そのもとにブレーンとして地域の読書好きのサークルなどを加えるのもよかろう。
つまり、実務をこなすものと、精神的な仕事をするものを分離しなければならないということである。ところが実際には、両者は分離されていないうえに、精神的な仕事のほうは、その存在さえ危うい。しかも、その精神的な仕事が、実務者の意志によって浸食され、実務者の都合のよいように動かされてしまっている。この状態こそ、官僚支配、官害、と呼ばれるものの正体である。
だから、官僚支配の弊害を是正する為にやるべきことの第一は、実務者と精神的な仕事をするもの(これを目的者と仮に呼ぶことにする)を明確に区分けすることである。
実務者は実務のみをやる。目的者は目的を達成する為の方策を探し出し、実務者に実行させる。もしもその行政サービスの評判が悪い場合には、担当の目的者が左遷されることになる。左遷された前任者にかわり、広く役所外からも人材を求めるて業務改善を促進させるべきなのだ。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

from: 一久さん
2006/02/11 21:11:42
icon
「芸人と官僚」官僚病の分析官界に限らず、すべての職業は官僚病にかかる因子を持っている。すべての職業には、実務を無難にこなすという目的と、より改良された
-
-
from: 一久さん
2006/02/11 01:25:45
icon
ムハンマド風刺画問題
ムハンマド風刺問題について風刺画がイスラム社会からの抗議にも関わらず、掲載され続ける理由を考えてみた。経済的な利益狙いというようなものは除いて。理由:
ムハンマド風刺問題について
風刺画がイスラム社会からの抗議にも関わらず、掲載され続ける理由を考えてみた。経済的な利益狙いというようなものは除いて。
理由:1
テロルに屈することになるから。
イスラム側の抗議行動がすでに暴力をともなったものになっている以上、これに応じる形で掲載を止めたり謝罪することは、言論の自由がテロルによって処断され、以降監視されるようになることを意味するからである。すなわちこれ全体主義である。宗教上の対立といえども、抗議はあくまでも法律の範囲内でなされなければならない。言論の自由は、行為の自由ではない。無法行為が許される訳ではない。テロルに走る者には、言論の自由はない。彼らは自由の敵とみなされるのである。
理由:2
イスラム社会に対する不信感
このような問題が起きると、必ずイスラム教徒側からは、テロルをするのは一部の者だけだという声明が出される。それは真実ではあろう。だが、ムスリム以外の者は、ではその「善良な多数のイスラム教徒」が、テロリストの逮捕や摘発に熱心に協力しているのか、という疑問をもっている。表向きはテロルを批判しているが、内心では喝采を送っているのではないのか、消極的協力者としてテロリストの炙り出しに無関心であるのではないのかという疑いが持たれている。
テロリストではないイスラム教徒自身が、他の誰よりも積極的にテロルを取り締まるのでない限り、この疑いは払拭されることはない。
だが、そんなことができるのだろうか。テロリストといえども、ムスリムにとっては彼らもまたイスラム教に殉じようとする熱心な信者である。テロはいけないが、気持ちは分かる。そんな「犯人」を警察に自分の手で突き出せるのであろうか。
欧米や日本では、それができる。「法の支配」のほうが、宗教よりも重要視されるからだ。大石蔵之助と赤穂浪士は、仇討ち後に自ら出頭した。法の支配を一時的に破った責任をとる為である。けっして、江戸市中に紛れて逃げようとはしなかった。それこそが近代国家というものである。イスラム社会にそれができるだろうか。
欧米の新聞に風刺画が載ることを容認する、欧米社会の精神的背景は、まさにここにあるのではないか。なんだかんだ言って、テロリストをかばっているんじゃないか、と。それでは、ムハンマドがテロに関与しているかのようなマンガを書かれてもしかたがないじゃないかと。
ここで問題になるのは、「法」が上か、宗教が上か、ということである。近代国家に生きる我々は、当然に「法」の優位を信じることができるけれど、イスラム教徒にそれができるのかどうか。彼らにアラーの言葉よりも「法」のほうが大事だと承認させることができるのだろうか。
これを認めること、それこそが「宗教と政治の分離」の根本であり、そこからしか近代国家は生まれないのである。産業革命以前、欧米を凌駕していたイスラム経済圏で、近代化がなし遂げられることがなかった原因もここにある。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-




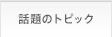




from: 一久さん
2006/03/04 20:17:26
icon
「とんでも八分,もう十分?」陰謀説いくらなんでも、陰謀説はないでしょうねぇ...まあ、東大の入試に、「裏のとり方」なんて出題されませんから。大蔵省では