-
from: shantiさん
2006/07/27 17:48:37
icon
アシュタンガヨガ(パタンジャリヨガ)...第3ステップ
皆さん、こんにちは。shantiです。5月29日付のスレッド[216]でアシュタンガヨガ第1ステップについて、7月28日付のスレッド[461]でアシュ
皆さん、こんにちは。
shantiです。
5月29日付のスレッド[216]でアシュタンガヨガ第1ステップについて、7月28日付のスレッド[461]でアシュタンガヨガ第2ステップについてご紹介しました。 サンスクリット語で‘8’という意味のアシュタ。 今日はその8つのステップのうちの3番目です。
1番目は「ヤマ(YAMA) 」でした。
2番目は「ニヤマ(NIYAMA)」でした。
「ヤマ」が外のもの、社会に対する心のコントロールであるのに対して、「ニヤマ」は自分自身に対する心のコントロールでした。 それぞれ5つずつありました。
3番目は「アーサナ(体のポーズ)」です。 ここでやっと、ヨガマットの登場です(?)
「アーサナ」はサンスクリット語の「アース(座る)」という動詞からの派生語だそうです。
「アーサナ」とうのはヨガをする人たちが瞑想をする時に取る、じっ〜と座ったポーズに繋がっていくそうです。
なので、本来「アーサナ」というのは忙しく体を動かす動作そのものではなく、その同じポーズでじっとしている所にポイントがあるようです。 だから、ヨガでポーズを教わったときに、“最終的にはこのまま3分じっとしていられるようになればいいです”、などという解説がなされると思います。
以前にも書きましたが、普通のストレッチ体操と違うところはそのポーズをじっとしているときに呼吸を見つめ、伸びている体の部分に気持ちを持っていくことです。 この、“気持ちを一つの方向に向けていく”ことで、瞑想に繋がっていくそうです。 だから、「アーサナ」は一種の瞑想でもあるとも言えるそうです。
「ヤマ」「ニヤマ」が先にあってそれからやっと「アーサナ」が出てくるということは、ヨガの本来の目的からいえば、いくら体が柔らかくて綺麗にポーズが出来た所で、心の面での訓練が出来ていないとそれはそこまでのものだ、ということだそうです。
ヨガを教える人は自分の経験を踏まえて教えないと、本当の教えにならないといわれます。 (ヨガでなくても学校の先生でもそうだと思いますが。 生徒に言ってる事と自分のやってることがずれてる先生がわが子の担任だとちょっと嫌な気分ですよね。)
インドでは、「ヨギ(女性の場合はヨギニ)」という言葉が使われますが、それはヨガに精進し、心も体も魂も綺麗な人で、自分が宇宙の一部であるとの認識に達し、いつも幸せに満ちている人だけに使える言葉です。 「ヨギ」という言葉はそれほどすごい意味の言葉なので、本人から自分の事を「ヨギ」と呼ぶよりはむしろ、人から見て本当にその人がヨガに精通し、困っているものを救おうとし、愛に満ちてスゴイと思われたとき、「ヨギ」と呼ばれるようです。 (インドでは、です。)
「アーサナ」のことについては、“ハタヨガ”というもの(知っておられる方もいらっしゃると思いますが)について、書く機会があるときに触れたいと思います。
それでは。 (今日は比較的短く済みました!(^^)!
from: おみゃーさん
2006/08/07 23:58:16
icon
「Re:「ヨギ」と言う言葉」shantiさん、こんにちは。いや全然横道じゃなくって、まさに知りたいことを教えていただきました。私の行くヨガスタジオの先
-
from: shantiさん
2006/07/26 00:07:08
icon
インドとカースト制度
こんにちは、皆さん。shantiです。>インドはカースト制という未だに身分に階級がついてますよね。だとしたらあの男の子身分の高い家の子だからあれだけ大
こんにちは、皆さん。
shantiです。
> インドはカースト制という未だに身分に階級がついてますよね。だとしたらあの男の子身分の高い家の子だからあれだけ大騒ぎして助けられたんではないかと?偏見かもしれませんがどうなんでしょう?
マップルさんのメッセージが気になったので、主人に聞いてみました。 カーストの高いとか低いとかはわからないのですが、農業に携わっている家族だそうです。
インドと言うと、カースト制度、とは、私も歴史で習った記憶がありますが、それ以上のことはわかりませんでした。 逆にインドで「日本にもカースト制度があったんだそうですね?」と聞かれたときは一瞬何のことだかわかりませんでした。
元々インドではカーストというのは職業をさすものの言葉のようで、例えば戦うのが好きな人は武人のカースト、本を読んだり勉強をするのが好きな人は学者のカースト、商売が好きな人は商人のカースト、....というような感じだったそうです。 だから、カーストは生まれで決まるのではなく、例えば、商売のカーストの子供が、戦いが好きでそういう騎士になったら、その子は武人のカーストということらしかったのです。
それを日本の士農工商みたいに生まれで固定したのは僧侶のカーストの人たちだそうです。 そのほうが人々を制御しやすかったからだそうで、インドのもともとの良き文化を僧侶が台無しにした、ということだそうです(家族が僧侶の人もそれを認めていました)。
世の中を支配したいと思う人たちの考えることは、皆同じなんでしょうか?
今、都会では多くの若い人たちはお互いのカーストなんて知らないそうですし、結婚もあまり気にしなくなってきているようです。 ただ、田舎ではまだまだそれにかなりこだわる所もあるようです。 長い間インドの社会に根付いてきたものなので、そう簡単には払拭できないとは思いますが、時代が新しくなっていくにつれ、消えていくと思います。
それにしても、元々カーストが自由に変えられるなんていうことを知らなかったので、新たな発見をここでしました。 -
from: つねきちさん
2006/07/26 07:31:32
icon
季節
松本は久しぶりに朝から青空が見えてます毎年夏になると暑いね〜冬は寒いね〜なんて言ってますがやはり夏は暑く冬は寒くならないと自然のバランスが狂ってしま
松本は久しぶりに朝から青空が見えてます 毎年夏になると暑いね〜 冬は寒いね〜 なんて言ってますがやはり夏は暑く冬は寒くならないと自然のバランスが狂ってしまいます 農作物も育たないしプールやスキー場も人が来ないから景気も上がりません 自分はバランスという言葉を大切にしています 健康、仕事、人間関係、ヨガすべてバランスが必要ですよね〜
from: shantiさん
2006/07/26 12:07:23
icon
「バランス」こんにちは、皆さん。つねきちさんの仰るとおりですよね。夏は暑く、冬は寒く。インドの昔の考え方では、以前書いたように、人間の体は5つの要素で
-
from: shantiさん
2006/07/23 16:14:50
icon
ゴマの花と実
皆さん、こんにちは。shantiです。長々と硬いメッセージを送ってしまったので、ここでちょっと一休みです。白いゴマの花とすぐ左の隣のふっくらしたのがゴ
皆さん、こんにちは。
shantiです。
長々と硬いメッセージを送ってしまったので、ここでちょっと一休みです。
白いゴマの花とすぐ左の隣のふっくらしたのがゴマの実のサヤです。 中にゴマがいっぱい入っています。 北インドのカジュラホっていう所に行った時にゴマ畑で撮りました。 ゴマの花なんて初めて見ました。
-
from: マップルさん
2006/07/18 02:08:14
icon
突然ですが
こんばんわ。初めてのカキコでいきなりなんですが、僕は「精神世界」の話が好きです。インドも好きな場所です。一度は行ってみたい。(前世はインドの商人でした
こんばんわ。初めてのカキコでいきなりなんですが、僕は「精神世界」の話が好きです。インドも好きな場所です。一度は行ってみたい。(前世はインドの商人でした。(^o^)
http://www.gaiasymphony.com/
この映画は素晴らしいです。機会があればぜひ、一度見て下さい。
ちなみに僕は1〜4まで見ました。
あなたの心に響くメッセージがあることを願って。 -
from: shantiさん
2006/07/22 16:17:23
icon
頭立ちのポーズ
こんにちは。おみゃーさん、メッセージ有難うございます。示されたHPを見せて戴きましたが、綺麗なポーズは載っていましたが、そこでの教え方のポイントとかは
こんにちは。
おみゃーさん、メッセージ有難うございます。
示されたHPを見せて戴きましたが、綺麗なポーズは載っていましたが、そこでの教え方のポイントとかは載っていなかったように思うので(英語だから見過ごしたかもしれませんが(^_^;)、何処をどうとか言い辛いのですが。
> 頭立ちのポーズで、頭をつけずに前腕で身体をささえようとしても2〜3秒で崩れて頭が付いてしまいます。
頭はつけて戴いていいですよ。頭をずっと浮かしていることが出来たらそれこそ物凄いコントロールがいると思います。 頭はつけているのですが、体重がずしっと頭だけにかからないということです。 体重がかかると、仰っているように首の骨がぐっと上下から抑えられるような感じがします。 体重のほとんどは前腕で支えています。 肘の間隔が広がっていないか確認して下さい。 私はたまに肘の間隔を測っても、手を組んだときに多少広がっているような感じがするときがあるので、また組み直すことがよくあります。 肘が広がると辛いですね。 それと、頭の後ろだけを手で支えるだけでなく、“気持ち”頭を手に乗っけて頭を手で覆うようにするとちょっと楽になります。
取りあえず、質問だったので書いてしまいましたが、お一人でされるといくらおみゃーさんが頭立ちができると言ってもとても危険だと思います(頭や首のことなんで特に)。 私達が側にいられればいいのですが、そうでないので、おみゃーさんが習われた通りにされている方がいいかもしれません。 慣れているほうがいいでしょうし。
ただ、こういう考え方で、頭に体重を乗せるのはよくないと昔のヨガは言ってたんだな、という程度でも構いませんので。
それと、前にも書きましたが、昔の人は頭立ちで気の遠くなるような長い時間、しかも毎日されていたようですが、それは今の時代では止めた方がいいそうです。 せめてやって30秒。
確かにこのポーズは他にたくさんあるアーサナーの王と呼ばれているようで、呼吸法やスーリヤナマスカー(太陽礼拝)の次、すべてのアーサナーの最初にやる、とても効果のあるアーサナーらしいですが、すべての血液、体液が脳の方にさーっと上っていきます。
人の体やこの世のすべてのものは5つの要素から出来ていると昔のインドの考え方では言われていますが、その要素、大地や水や空気...今はすべて汚れている時代です。 そしてそんな中で生きている現代の私達の体も残念ながら汚れているのです。 綺麗でない血液や体液を脳に過度に送り込んでいくことにより、汚れたものが脳に溜まっていって何十年か後にはその影響が出てきてしまうというのです。
色々な本には確かに、最初は15秒ぐらいで徐々に時間を増やして5分とか10分とか書いてありますが、以上のような理由でそんなに長くやらないほうがいいらしいです。
また、これを読まれた方で、“頭立ち? そんなの雲の上、前屈もだめなのに”、と思っておられる方は、頭立ちができないとヨガじゃないと思われればそれは間違いなんで(確かに出来ると、カッコイイかもしれませんが)。 それは今までずっと書いてきた理由からです。 頭立ちができなくてもウサギのポーズで十分ですから。
長々と書いたわりに、満足のいくお答えになっていなかったらすみません。 また出直して考えますので、いつでもメッセージ下さいね。 -
from: ゆうさん
2006/07/12 19:28:36
icon
教えてください
shantiさん、皆さんお久しぶりです。しばらくサークルをのぞいていなかったので、メッセージを読破するのに少し時間がかかりましたが、読破しました\(^
shantiさん、皆さんお久しぶりです。
しばらくサークルをのぞいていなかったので、メッセージを読破するのに少し時間がかかりましたが、読破しました\(^0^)/
いつも勉強になります。
shantiさん、そちらはいかがですか?大丈夫でしょうか?
今日はshantiさんに教えていただきたいのですが・・・
9月にシバナンダヨガのワークショップに参加するのですが、その時来日する先生が、スワミ・チェータ師という方だそうです。
shantiさんの知っていらっしゃる方でしょうか? -
from: shantiさん
2006/07/18 00:30:58
icon
頭を床につけるヨガのポーズ
こんにちは、皆さん。世界中が大変です。テロ、ミサイル、爆撃、火山噴火、地震、津波、大雨...。加えて人間関係の不調和、仕事での摩擦...。本当に私達は
こんにちは、皆さん。
世界中が大変です。 テロ、ミサイル、爆撃、火山噴火、地震、津波、大雨...。 加えて人間関係の不調和、仕事での摩擦...。 本当に私達はなんて世界に生きているんでしょう。
さちさんが以前仰っていた、“地球が怒っている”というのは見過ごすことの出来ない言葉かもしれませんね。
興味深い話があるのですが、それはちょっと置いておいて、あっこさんの質問です。
> うさぎのポーズみたいに頭の頂点を床につけるようなポーズありますよね?あのようなポーズで頭をつけていくと頭(髪の毛)がマットにこすれるような感じがして(その時に髪の毛が摩擦で抜けちゃうような感触) それがいやだなぁと思ってるんですけど、そうならない方法ってありますか??
確かに頭のてっぺんを床につけるポーズの写真は日本で本を見たときもいくつもありました。 頭で立つポーズ、魚のポーズ、ウサギのポーズ(実は名前とポーズが一致しなくて、最初どんなポーズかわかりませんでした(^_^;)、またそれぞれのバリエーション...。
頭のてっぺんには確かにポイントがあり、そこを適度に刺激するのはいいようです(指圧なんかでは頭のてっぺんをきゅーっと押したりすることもありますよね)。
ただ、昔のヨガの考え方では頭はとても大事でデリケートな所なのでどんなポーズをするにしても圧を加えてはならないそうです。 (指圧で押されるのは、ちゃんとした専門家の方ですしね。)
だから、私達は魚のポーズでもウサギのポーズでも頭のてっぺんを床につけません。 だらんと首の力を抜いて垂らしているだけです。 頭立ちのポーズでは頭に圧はかかっておらず、圧は両方の前腕(肘から先)にかかっています。
例えば魚のポーズにしても、頭をつけたときと頭をつけないときとでは、全く感じ方が違うのに気づきます(すみません、お一人では試してみないで下さいね)。 魚のポーズでは胸が開き、喉も開くので体によい効果があるのですが、頭をつけていると明らかにその開きが小さくなってしまうのです。
確かに私達もポーズのバリエーションの中で頭を床につけることはありますが、決して圧を加えず、ただちょっと触れているだけという感じです。 頭がマットにこすれる感じがするほどつけるのは明らかに体重の半分位(?)を頭で支えてしまっていることになります。 ウサギのポーズにしても、立てたかかとの上にお尻を乗せて背中を出来るだけ丸めて、首の力を抜いて頭をだら〜んと垂らしているととても気持ちがいいです。 頭を床につけているときとは全く感じが違います。 (でもこれも無理に試さないで下さい。 ちゃんと要領がわからないと、変に首に力が入ってかえって首の筋肉が突っ張っちゃったりするかもしれませんから)。
ちなみにこのウサギのポーズは頭が体のすべての器官より低い位置に来るので、血液が脳にザーッと流れていきます。 この意味では頭立ちと同じ効果があります。 だから、頭立ちをしなくてもこれで同じ効果を得ることが出来ます。 こっちの方が安全ですしね。
それと、頭立ちが出来る方は長くとも30秒以内までにした方がいいそうです。
あっこさん、こんな感じで納得できる答えになったでしょうか?
何かあったらまたメッセージ下さいね。 -
from: つねきちさん
2006/07/19 14:33:47
icon
shantiさん
御心配していただきありがとうございます私の住んでいるところは大きな災害もなく今は雨も上がってます車で数十分の諏訪や天竜川は決壊して数名行方不明になって
御心配していただきありがとうございます 私の住んでいるところは大きな災害もなく今は雨も上がってます 車で数十分の諏訪や天竜川は決壊して数名行方不明になっています 自然災害には人間何もできないですね 宇宙に行ったり科学を自由に操ることができても自然には歯がたちません信州の大自然はとてもきれいですが反面恐さも半端じゃないです
-
from: shantiさん
2006/07/21 18:28:44
icon
アーユルヴェーダ...自然派化粧品(?)
こんにちは、皆さん。shantiです。久々にアーユルヴェーダ編の肌への療法を。①コップ1杯の牛乳を沸騰させて、ライム1個の汁を絞り、小さじ1のグリセリ
こんにちは、皆さん。
shantiです。
久々にアーユルヴェーダ編の肌への療法を。
① コップ1杯の牛乳を沸騰させて、ライム1個の汁を絞り、小さじ1のグリセリンを加えて30分置いた後、顔、手、足に寝る前につける(なお、グリセリンは入れすぎるとかえって肌が乾燥するそうです)。
② レモンの汁とヨーグルトを程よく合わせて、自然のクレンザーに(傷があるときはひりひりするのでヨーグルトだけの方がいいかも。 ターメリック(ウコン)の粉をほんの少し混ぜるとなおいいです)
③ ヨーグルトで髪をよくマッサージすると髪を健康にする(乾燥肌の人は地肌も健康になると思います)。
今日はこの3つで簡単に。
毒になるものはないと思いますので、ご興味のある方は試してみて下さい。
それでは。from: shantiさん
2006/07/22 15:15:13
icon
「自然のクレンザー(?)説明追加です」こんにちは、皆さん。shantiです。スレッドの[469]で説明した②ですが、ヨーグルトを塗ってしばらくマッサー




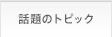




from: shantiさん
2006/08/12 18:41:22
icon
「グルクラ」おみゃーさん、こんにちは。参考になったようで、よかったです。ヨガの先生は生き方も教えてくれますよね。それを通じて、周りのものと調和して生き