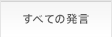サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: エリスさん
2012/02/24 11:20:17
icon
「双面邪裂剣(ふたおもて やみを さく つき)・43」
枝実子の部屋。その箪笥の前で景虎は眠っていた。如月は、そうっと近づいて、手を伸ばした。すると……。
「フゥーッ!!」
景虎がすぐさま目を覚まし、如月に唸り声をあげる。如月はフッと苦笑いを浮かべた。
「主人思いの子猫だと。だが……」
如月は掌を向けて、黒い気を放って景虎を弾き飛ばした。
「所詮は小動物であろうに、小賢しい」
苦しみながらも、景虎は立ち上がろうとする。如月にはその姿が、不愉快でしかなく、首元を摘み上げると、床に叩きつけた。
「先ずは、おまえから始末しましょう」
景虎が守ろうとしていた箪笥の最下段。そこに片桐家宝刀・白陽は眠っていた。
「瑞樹が来るのは危ない。如月には、最後まで瑞樹の記憶が戻っていることがバレ方がいい」
と枝実子に言われ、瑞樹は章一の家で待っているしかなかった。
「まあ、お茶でもいかが? お菓子もあってよ」
章一の母はリビングに彼女を招いて、あれこれと世話を焼いてくれた。
「あ、すいません。私までお世話になっちゃって」
「いいのよ。枝実子さんは章一の大切な人だし、その枝実子さんのお友達なんですもの。遠慮しなくていいのよ」
「良かった。エミリーはここの家の人にも愛されてるんですね」
「あら。あの子を嫌いになる人がいるの?」
「う〜ん、少しだけ」
瑞樹は枝実子の両親のことを思っていた。どんな経緯があるのかは知らないけど、枝実子が両親に愛されていないのは、見ていれば感じる。
眞紀子や真田の場合は、嫌っていると言っても、きっと表面だけなのではないかと、彼女は考えていた。
『そうだよ。特に真田さんの方、絶対に不自然だよ、あんな離れ方は』
玄関のチャイムが鳴ったのは、瑞樹がそう考えている時だった。
章一の母はすぐにインターフォンに出て、それから玄関の戸を開きに行った。
「夜分に突然失礼いたします。我が校の生徒がこちらでお世話になっているはずなのですが」
「我が校と言われますと?」
玄関から聞こえてくる声を聞いて、あれ? と思った瑞樹は、自分も玄関へ行ってみた。
「私、御茶の水芸術専門学校で講師をしております、日高……」
「佳奈子先生!?」
瑞樹は相手の顔を見るなり言った。
訪ねてきたのは、日高佳奈子女史だったのである。
二人は枝実子の家へ向かっていた。あたりは月が映えるほどに、暗い。
家の傍までくると、誰かが玄関から出て来るのが見え、二人は身を隠した。
出てきたのは如月だった。藤色の一つ紋を着ている。
腕に小さなものを抱えている――景虎らしい。
『景虎、随分おとなしいな』
枝実子は思いながら、章一と、如月の後を付けて行った。
彼が向かったのは、近くを流れる川の土手だった。土手には子供が川に落ちないように柵がしてある。如月は、その前に立つと抱えていたものを摘み上げた。
思わず二人とも声をあげそうになった。景虎は傷だらけだったのだ。そして、今にも如月が川へ投げ入れようとしている。
「景虎!!」
枝実子が叫んだのと、章一が走り出したのは同時だった。章一は、如月の手から離れた景虎へ向かって、柵を踏み台にして飛び上がった。――そのまま、川へ落ちるかと思った。が、章一は危うく堤防を張っていた蔦に掴まって、景虎ともども助かった。
「貴様ァ……よくも景虎をォ!!」
枝実子は怒りで右手を握り締めていた。
「小動物如きがわたしに逆らうからですよ」
「ふざけるなッ!!」
枝実子は渾身の力で殴り掛かった。だが、如月はスッと消えたように避けて、行き過ぎた枝実子の背後に左手を向けた。
如月の掌から、どす黒い霧が発生する。その霧は枝実子を包み、章一が景虎を抱えて岸に這い上がってきた時には、巨大な繭玉と化していた。
「エミリー!!」
繭玉に閉じ込められた枝実子は、恐ろしいほどの悲哀を感じていた。
悲しみだけではない。心臓を止めるかと思えるほどの痛み、劣等感、敗北感、人間の感情の中で“辛い”と思えるものを総て、思い知らされていた。
「苦しいであろう」と如月は嘲笑った。「今、御身が味わっている苦しみは、御身が他人に与えてきた苦しみを総て集めたものなのですから」
九条真紀子の、真田光司の、そして、前世において、彼女が蒔いた不和の種によって引き起こされた戦争での戦死者、その家族の悲しみと憎しみが、一度に枝実子に降りかかる。
「あっ……あっ……」
口は開いているのに、恐怖が強すぎて悲鳴にならない。
「そう、もう一つ……忘れてはならない物が。御身が邪(よこしま)な想いを寄せてきたおかげに、罪に問われて焼き殺された乙女の恨みの声を……」
それを聞いて、章一がハッとした。
「やめろ! あれはッ」
繭玉がさらに大きくなる。章一はそれを力強く叩いて、枝実子に訴えかけた。
「惑わされるな! あれは君のせいじゃない。君のせいだなんて、思ってない!」
如月はそんな章一を嘲笑った。
「無駄なことを。中のエミリーにそなたの声など聞こえはせぬ……そろそろ精神も限界に来たであろうか?」
「貴様ァ……」
章一は、左手に気を集めた……薄緑色に光るオーラが、玉となって膨れていく。そして、
「エミリーを放せ!」
と叫ぶと同時に、それを如月に投げつけた。
如月はそれを簡単に片手でキャッチした。薄緑色のオーラの玉が、だんだんと黒く変じ、彼はフフッと笑うと、それを章一に投げ返した――避ける間もなく、章一は玉に弾き飛ばされていた。
「多少、気功術を習ったからといって、前世の霊力の半分も扱えぬものを、生意気にも歯向かおうとは……まあ、無能なエミリーよりはマシであろうが」
景虎を庇いながら倒れた章一は、その衝撃で左肩を痛めてしまう。
確かに如月の言うとおりだ。前世であっても、神族とは言え半分人間の血が混じっていた彼である。それほど霊術に詳しかったわけでもないし、ましてや今は完全な人間の器だ。
『畜生、エミリーなら……彼女が前世のように霊力を使えれば、こんな奴……』
既に勝ち目はないのか――そんな時だった。
「清浄なる総ての光よッ」
と、誰かの声が響いてきた。「太陽神の名において、カナーニスが命ずる。我が手に集(つど)いて剣となれ!」
見ると、いつの間にか脇に車が停められていて、そこから一人の女性が走ってきた。
彼女の手に光が集まり、諸刃の剣となっていく。そして、その剣で繭玉を切り裂いた。
意識を失って倒れてくる枝実子を、彼女は咄嗟に受け止めた。――その人物は、日高佳奈子女史だった。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/17 11:48:04
icon
「双面邪裂剣(ふたおもて やみを さく つき)・42」
瑞樹が通された部屋は、枝実子の私室だった。引き戸を開けると、箪笥の前で丸くなっていた景虎が目を覚まし、見覚えのある顔を見て嬉しそうに「ニャー!」と鳴いてみせる。瑞樹は、枝実子が一番心配していた子が元気そうにしているので、良かったね、と胸の内で枝実子に話しかけた。
「景虎、お客様がいらしたのだから、お兄ちゃんの部屋にでも行っていなさい」
如月は微笑みながら景虎に近づき、膝を突いて手を差し伸べた。すると、
「フーッ、ファ!!」
と、唸りながら彼の手に噛みつこうとしてきた。如月が素早く手を引っ込めても、まだ唸り声をあげている。絶対にその場を離れない気である。
「いいよ、エミリー。邪魔にはならないし、それより、あまり日にちがないんだから、すぐに本題に入るよ」
瑞樹は自分から部屋の奥――景虎の前になるように、ちゃぶ台の傍に敷かれた座布団に座った。
「いったい、どんなストーリーなら納得して演技してくれるのよ」
いきなり強気な態度を取る瑞樹に、如月は苦笑して見せた。
「あなたが妥協ですか。珍しいこともあること」
「日にちがないって言ってるでしょッ。発表は秋の文化祭なのよ。今は何月?」
「まだ四月でしょう」
「そう、ゴールデンウィーク間近のね。本当なら、今頃脚本の書き直しなんかあってはならないのよ」
「わたしには十分に時間があると思いますが」
「いいから、とにかくあんたも座って!」
と、瑞樹は自分の向かい側を指さした。先ずは彼を景虎から引き離さないことには、景虎が唸りを止めないと思ったからだ。枝実子が心配していた通り、やっぱり景虎は如月に反抗している。
『でも、だったらどうしてこの場所にいるの?』
瑞樹が不思議に思っていると、遠くから枝実子の母親の声が聞こえてきた。お茶を入れたのだが、更年期障害が始まっている枝実子の母ではお盆を持って歩くのは辛いので、枝実子(如月)に取りに来てくれと言っているのだ。
如月が『しょうもない』と思いながら部屋を出て行くと、ここぞとばかりに瑞樹は景虎に話しかけた。
「私の言葉わかるよね? 私ね、本当のエミリーに頼まれてここに来たんだよ」
景虎はすごく嬉しそうな顔(瑞樹にはそう見えた)をした。
「ねえ、如月に反発するぐらいなら、別の部屋にいた方がいいんじゃない?」
景虎は小さく鳴いてみせた。駄目だと言っているようだ。
「どうして? もしかして……」
ここに居なくてはならない理由がある?
そうか! と瑞樹はすぐに思いついた。景虎がいる向こう――箪笥の中に、なにか大事なものがあるのだと。
それは、もしかしたら如月の弱点になるものでは。
考えてみれば、枝実子は古めかしいものを集めるのが好きで、片桐の祖父からもいくつか譲ってもらったものがあると言っていた。その中に、如月が嫌いな――聖域・近江の国ゆかりの物があるのかもしれない。
瑞樹はそうっと手を箪笥に近づけてみた。すると、ペシッと軽く景虎がその手を叩いた。
「え? 駄目なの?」
その時、誰かの足音が聞こえてきた。如月が戻ってきたのだ。
『如月に見つかるかもしれないから、止めたのかな?』
瑞樹はそう思いながら、何もなかったかのように振る舞っていた。
「あのヤロー……」
新しく出来上がった脚本を見て、枝実子はそう言い捨てた。
如月が瑞樹に作り直させた内容は、枝実子の想像を絶するものだったのだ。まるで、この世の総てを呪うかのようなストーリー……。
「しばらくはこの通りに稽古をつけとく」
瑞樹も頬杖を突きながら言った。
ちなみにここは章一の部屋である。
「だから、エミリー。早くあいつをなんとかしてよね」
「みんなにも迷惑かけちまうな」
「悔やむのは後。それじゃ、今日の報告をするよ」
瑞樹は如月を訪ねたときのことを、できるだけ詳しく説明した。
説明を聞いて、枝実子はしばらく考えていた。
「何か思いつくものはあるの? エミリー」
章一が話しかけると、おそらく……と、枝実子は話し出した。
「景虎が瑞樹を制したのは、如月に気付かれるから、というよりは、隠して持ち出せるものじゃないからだと思う」
「そんなに大きなものが仕舞ってあったの?」
「ああ……近江につながりがあるとすると、あれしかないからな」
「もったいぶらずに教えてよ。なによ、それ」
「白陽(びゃくよう)だ。片桐家に伝わる刀だよ」
片桐家には、古くから伝わる二本の刀があった。それは佐々木家から分かれ、桐部氏となった時、当時の佐々木家の長(おさ)より授かったもので、近江の刀匠が琵琶湖の畔に小屋を建てて神に祈りを捧げながら打ったものだと言い伝えられている――その後、桐部氏から分家して片桐家になった時に継承された。一本は月影(つきかげ)と言い、それまで長女を神宮の斎姫(いつきひめ)として差し出してきた片桐家が、親鸞聖人(しんらんしょうにん)と出会い帰依したことで、最後の斎姫となった鏡姫(かがみひめ)が自分の柩の中に入れさせて、ともに墓所に入ったと伝えられている。そしてもう一本を白陽という。これは現代に残されており、片桐家の後継者に手渡されることになっている。
「つまり、俺が預かっている刀のことだ」
「それを、景虎ちゃんが守っているんだ!」
瑞樹が言うと、章一は、
「猫は霊力が強い。景虎が守っているってことは、如月を倒す切り札になるだけのものってことだ」
と言って、枝実子を強い瞳で見つめた。「行こう、すぐに」
「行こう」
枝実子も力強く立ち上がった。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/10 12:45:02
icon
「双面邪裂剣(ふたおもて やみを さく つき)・41」
「もう一度洗脳しようとしても、無駄よ」
眞紀子は如月を解放してあげてから、色っぽく微笑みながらそう言った。
流石の如月も、動揺が隠せない様子で、ただ立ち尽くしている。章一の他にも、魔力で操れない人間がいようとは……いったい、何故?
「どうしてあなたがエミリーさんじゃないって分かったか、不思議に思っているのじゃない? 教えてあげるわ」
眞紀子はテーブルの傍に来て、如月の方のティーカップを手にした。「これよ」
「……紅茶?」
「そう。エミリーさんはね、ただでさえ太りやすい体質だから、あまり甘い物は取れないの。だからお茶に砂糖は入れない――そこまではあなたも同じね。でも、基本的には甘党の彼女は、どうしても他のもので甘さを補おうとする……だから、紅茶にはミルクを入れる。それも大量に……それから、これが決定的なのよ。彼女は酸味が嫌いなの。酢の物はもちろん、蜂蜜水を作る時もレモンは大して入れないわ。だから、砂糖が入っていない上に酸味を加えた紅茶なんて、彼女が飲むはずがないの」
「……なるほど、あなたが確かめたかった事とは、こういうことでしたか」
如月はフッと苦笑いを浮かべて、テーブルの前の椅子に座った。
「気を付けて、そういう些細なことから、人は気付くものよ。これ以上、誰かにバレたくはないでしょう?」
眞紀子も如月の向かいに座った。
「このまま、黙って見逃してくれるとおっしゃるのですか?」
「見逃すどころか、協力してあげても良くってよ」
「何故ですか? 察するに、あなたは何もかも気付いておられるのでしょう。でしたら、わたしを気味悪く思うはずではありませんか? わたしは!」
そこで、眞紀子がスッと身を乗り出して、人差し指で如月の唇を止めた。
「水面に映る月。エミリーさんでありながら、全く別の人間。……それでいいの。それでいいのよ……」
眞紀子の微笑みに魅了されながら、如月は枝実子の思い出からコピーした自分の記憶を過去に遡っていた。
そう、彼女は枝実子に絶交を言い渡した時、言ったのだ。
「あなたが、全く違う人間に生まれ変わらない限り、あなたに会うつもりはなくってよ。……全く、違うあなたに……」
だからこそ、自分は――。
次の日の夕刻。
瑞樹は片桐家を訪問した。
当然のことながら、如月を探るためである。
あの後、片桐家に電話を掛けたところ、如月は眞紀子の家に招待されて留守だった。しかも、泊まってくるという。枝実子はそれを聞くなり「眞紀子さんの傍に置いておいたら危険だ」と、今にも眞紀子の家に向かおうとしたが、例のごとく章一が後ろから羽交い絞めにして引き留めた。
「大丈夫だよ。君が考えているような、不埒な真似は恐らくしないだろうから」
「だって、あいつ! 男じゃないか!」
枝実子は、『しかも俺から生まれた』と胸の内で思っていたが、そこまで口に出さないように感情を押し止めた。
瑞樹も枝実子とは違う意味で、同じことを心配していた。
「眞紀子さんって、清楚に見えながら結構色っぽいのよ。しかも夜になって雰囲気が出てきちゃったら、どんな男でも狼になりかねないって」
「そういうこともありえるけど」と章一は言った。「大丈夫だよ。如月なら思い止まるから。と言うより、我慢しなくちゃならない理由があるんだ」
「なんで!?」
と、枝実子と瑞樹は揃って言った。
「簡単なことだよ。巫女みたいなものなのさ」
「ミコ?」
瑞樹は分からなかったが、枝実子は「ああ……」とうなずいた。
「純潔でいないといけないからか」
「ハイ?」
「神に仕える巫女は純潔でなくちゃならない。そうじゃないと、神々の――もしくは自然や大地の霊力を体内に集めることはできないんだ。子供のころは良く幽霊とかを見ていたのに、結婚したり子供を産んだりしたら見えなくなったって話、聞いたことあるだろ? 子供――すなわち誰にも穢されていない体っていうのは、それだけ霊的に優れたものなんだ」
「ちょっと待った。それって変じゃない?」と瑞樹は言った。「だって、霊力の強い高僧にだって奥さんがいたりするし、霊媒体質の主婦だっているのよ。第一、子供を作る行為を“穢れ”として見ること自体が問題じゃない」
「だから、そういった人たちは」と枝実子は言った。「それなりに修行しているか、よほど霊力の強い守護霊がついているんだよ。それに、子供を作ることを穢れだって言ってるんじゃない。愛してもいない、愛されてもいない相手と交わると穢れになるんだ。愛し合っていればむしろ浄化される……そう、浄化されるんだ」
瑞樹は枝実子の出生の経緯を知らないから、彼女が自分に言い聞かせるように言ったこの言葉を、なんとなくしか理解できなかった。
「とにかく」と、章一が言った。「如月には、霊力を高めるための修行をしている暇なんかない。器の純潔と前世の記憶、それだけで霊力を使いこなしているんだ。エミリーを抹殺したいなら、自分から我が身を穢すことはしないはずだよ」
瑞樹にしてみれば、枝実子と章一の専門的な(ヤレ霊感だ、前世の記憶だといった)話は理解しきれないが、とにかく、如月が眞紀子に手を出すことはないであろうことだけは安心していた。
そう言ったわけで、一日たってしまったが、瑞樹は脚本の話し合いを理由に如月を訪ねたのだ。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/09 19:03:39
-
from: エリスさん
2012/02/03 13:24:41
icon
「双面邪裂剣(ふたおもて やみを さく つき)・40」
「あったま来た!」
再び瑞樹はこの台詞を吐いた。「あの女、この私まで洗脳してたなんて!?」
三人はカラオケボックスの中でジュースを飲みながら話していた。
「瑞樹、あいつは女じゃないよ」
枝実子にそう言われて、
「あっ、男だっけ。でも女にしか見えないけどね。美人だし、声も……言われてみると、あれ、エミリーの声なんだ」
「腹立つよな、ったくッ」
枝実子と章一は瑞樹に今までの経緯を説明し、如月の正体も明かしたのである。しかし、こんなに上手い具合にいくとは意外であった。
それについて瑞樹は言った。
「私が並の人間と違うからよ」
……まあ、そうかもしれないが。
章一は話を進ませる為に、今日の如月の様子を聞いてみた。
「麗子さんから面白い話を聞いたけど」
「どんな?」
「小説ゼミの時間にね……
日高佳奈子(ひだか かなこ)女史は、授業の終わりに如月を呼んだ。
「卒業制作のテーマを変えたいって、コースリーダー(分かりやすく言うと担任の先生)に願い出たそうね」
「はい。それがなにか?」
如月は愛想よく微笑みながら答える。
「あなたの、いいえ、片桐枝実子の制作監督は私がしているのよ。その私に相談もなく勝手に決めるなんて、どういうつもり」
「あのテーマがあまりに馬鹿げているからです」
「……そうね、あなたにしてみれば。すべてを憎悪していた頃の記憶を基本にして生まれたあなたなら、命をかけて一途な愛を貫いた女たちの生き様なんて滑稽でしょう。でも、エミリーは違うのよ」
意味の分からない会話をしている二人を、麗子は教室の外から見ていた。
「歴史の影に隠れてしまった十市皇女や倭姫皇后にこそ、真実の女の生き方を感じたのよ。押し込められた歴史の謎を、あの子は必死に繙(ひもと)こうとしているの。それをあなたに断念させる権利はないわ」
如月は冷ややかな表情になって、佳奈子女史を見つめた。
佳奈子女史も睨み返している。
しばらくして、如月が言った。
「お気づきのようですね、先生」
「あなたこそ、私が誰だか分かっているみたいだけど」
「あの男に、あなたのような娘がいたという記憶はありませぬが」
「知らなくても無理はないわ。私が生まれたとき、既にあなた――あなた達は眠りについていたものね」
「我らを嫌っているはずのあの男の娘が、なぜこのような所におられるのです」
「あなたは知らなくてもいいことよ」
そんなうちに、次の授業を受ける生徒たちが次々と教室の中へ入ってきた。
「そろそろ失礼します」
「待ちなさい、如月ッ」
佳奈子女史の言葉に、如月は振り返る。
「とにかく、テーマの変更だけは許さないわ。どうしてもエミリーに成り代わりたいなら、あの子がやらないような不審な行動は見せないことね」
「ご忠告はいたみいりますが、それはできない相談でございます。わたしは、近江(おうみ)の国(くに)とは性(しょう)が合いませぬ」
……っていう、やり取りがあったんだって。あんた達の説明を聞いてからじゃないと、理解できない会話だよ――聞いても分からないところ多いけど」
瑞樹のその話を聞いて、枝実子と章一は声を揃えて「近江の国とはッ」と言ってしまい、お互いに顔を見合った。そして枝実子が後を続けた。
「性が合わないって、言ったんだな」
「そう。なんか心当たりあるの?」
「近江は聖域なんだよ」
と、章一は言った。「最近、風水なんかでも言われてるけど、大地には気の巡る道があるんだ。地脈(ちみゃく)、または竜脈(りゅうみゃく)って言うんだけど。人間の体にもあるんだよ」
「血管みたいなもの?」
「うん、いい譬えだな。その血管は体の至る所に張り巡らされているけど、必ずある場所に戻り、そこからまた出発して血が流れているよね」
「心臓?」
「そう。地脈にも心臓にあたる重要スポットがあるんだ」
そこから枝実子が話を続けた。
「昔からそういう場所は、聖域、または禁忌の地として崇(あが)められ、恐れられてきたんだ。近江の国、特に淡海(おうみ)の湖(うみ)(琵琶湖)はまさにそれだろうね。この国の霊力を利用し、権力を手にしようとすれば、成功して繁栄を手にすることもあるし、霊力を扱いきれない者では破滅する。歴史を振り返ってみると、あそこに都が置かれたのはたった一度だけ。その時の天皇――権力者は天智天皇」
天智天皇が近江を統治し始めたころは確かに、繁栄に満ちていた。だが、その地で戦友である藤原鎌足を失ってからは歯車が噛みあわなくなり、やがて自分も病に倒れ、とうとう壬申の乱を引き起こしてしまう。壮麗な近江の都は崩壊してしまった。
それっきり、この国に遷都した事実はないが、この国を拠点に天下統一を目指した男がいた。安土城の主人・織田信長である。信長の偉業は誰もが知っていることだろう。琵琶湖の畔に築かれた安土城は、日本のみならず、海までも越えようとしていた彼の夢の象徴だった。だが、自ら第六天魔王と称した彼でさえもこの地を制しきる力はなかったのである――本能寺の変がそれを物語っていた。
「近江を制御できるだけの超人が現れるまで、近江遷都は考えてはならない。それ以外でなら、淡海の湖は人々に助力を惜しまないだろうけどね。近江の王族の娘・額田王(ぬかたのおおきみ)は、この土地で巫女の修行をしていたから、霊力のある女性になったって言われているんだ」
枝実子の話に、へぇ、と瑞樹は感心するしかなかった。雑学だけなら仲間内で誰にも負けないエミリーだけはある、と。
「だからエミリーは、自分の先祖が近江の出身っていうのが、密かな自慢なんだもんな」
章一が言うと、枝実子が微笑みで頷く。
「へえ、そうだったの……。でも、それと如月の近江嫌いと、どうつながるんだろう」
瑞樹が考え込もうとすると、章一が言った。
「だから、近江は聖域なんだよ。対して如月は闇の力を操る人間だ。聖域の光の力には弱いんだよ」
「ああ、そうか。如月は光に弱いんだ」
「と、言っても、ただの光じゃ駄目だ。聖域の光……霊力を持つ光じゃないと……。弱点が分かっても、どうすればいいんだか。それに……」
枝実子が口籠ると、なに? と章一は尋ねた。
「いや、大したことじゃない、よ」
大したことじゃない、わけがない。如月を倒す、ということは、彼を消滅させることであり、殺すことではないのだろうか。いくらこの世には存在しなかった人間とはいえ、人殺しというのは、果たして正しいことだろうか。現代は、そんなことの許された弱肉強食の時代ではない。
『俺にできるんだろうか、そんな恐ろしく、そして、汚らわしいことが………』
そう思った時だった。ふいに目に浮かんだビジョンがあった。――広野に何千人という男たちが、それぞれに武器を手にして、殺しあっている。どこか外国の戦場だろうことはすぐに分かった。だが、それを見ている視点が……今、自分が立っている場所がかなり上空だった。自分は何に乗っているのだろう。隣で鞭を振り、翼をもった馬を走らせて、その乗り物を走らせている、筋骨隆々な男がいる。その男の肩に手を掛けながら、自分は立ち上がってその光景を見ているのだ。そして、笑い声。嬉しそうな高笑いをしているこの声は、自分の声!
「エミリー!」
その声で、我に返る。
隣に章一が座っていた。
「どうかしたの? なんか、どっかにトリップしてた感じだったけど」
瑞樹が心配そうに覗き込むので、
「ああ、大丈夫だ」と、無理に微笑み、枝実子は言った。「それより、頼みがある」
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-