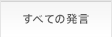サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: エリスさん
2013/09/27 11:05:40
icon
白鳥伝説異聞・15
「帰って来たことを、一番に報告に来ぬとは、親不孝者めが」
オオタラシヒコオシロワケ大王は、そう言いながら玉座に着いた。その時、王冠がずれて床に落ちたので、レーテーが拾って差し出すと、
「ああ、済まぬな。頭に乗せてくれぬか」
「はい、大王様」
レーテーはこれ幸いと、王冠を乗せつつ両手の親指で大王の額に触れた......。
大王の記憶を読んだレーテーは、気持ち悪ささえ感じたが、それを気取られぬよう努めて笑顔を見せた。
「嗅いだ事のない匂いだな」
大王はそう言って、レーテーの腕を掴んだ。咄嗟にタケルが駆け寄り、その手を離させようとすると、
「心配せんでも不埒なことはせぬ」
「そんなこと!」
信用できない――と、言おうとしたが、それをレーテーが微笑みで止めた。
『本当にこれ以上のことはしないつもりみたいよ』
と、レーテーはテレパシーでタケルに伝えた。大王はレーテーの匂いが嗅ぎたかっただけだったのだ。
「わずかだが、嗅いだ事のない、しかしとても良い匂いがする。これはなんだ?」
「恐れ入ります。この匂いを出会ったばかりで嗅ぎ分けられるとは」
それはエリスの娘たちに受け継がれた体香(たいこう)――ラベンダーの香りである。オトタチバナでいる間はこの匂いは隠すようにしていたのだが、僅かに残ってしまうのだろう。それを大王は嗅ぎ分けたのである。
「この香りは異国に咲く花の香り。我が母は生まれつきその匂いを体内から発することができ、娘である私もその力を受け継いでいるのです」
「ほう? ということは、そなたは異国の者か? 見た目では全然わからぬものだな。異国の娘が、何故我が国の姫神に仕えておる」
大王が手を離したので、レーテーは一歩下がって頭を下げた。
「これ以上は秘事にて、申し上げることができません」
「都合がいい言い訳だな。まあ、良い」
大王はそう言うと、今度はタケルの方を向いた。
「オグナ――いや、今はタケルと言ったか。見事、クマソタケルを討ち取ってくれたようだな。先ずは褒めてとらす」
するとタケルは、特に嬉しさも感じずに、
「恐れ多い事にて......」
と、仏頂面で答えた。
「しかし、妙な噂を聞いたのだが......そなた、女装をしておったそうだな」
「ええ。それが何か?」
「よもや、クマソタケルとそういう仲になったのか?」
下世話な!と、タケルもレーテーも思った......が、そこは耐えて、タケルが言った。
「たった一人で討ち取りに行ったのです。どんな方法を使っても成功させなければ、死ぬのはこっちですからね」
「そうか。まあ、クマソタケルの手が付いたところで、今更だがな」
すでに純潔ではないのだから、ということが言いたいのだ。実の父親がそんなことを言って娘を辱めるなど、やはりこの男は最低だ!――と、レーテーは思った。だがタケルは苦笑いを浮かべて、こう言った。
「私が女だったら、それでクマソタケルの血を引いた勇猛な王子が生まれたかもしれませんがね」
「ふむ、それは面白い」
と、大王が笑い出すので、それまで口をつぐんでいたヤサカノイリビメが言った。
「なんということをおっしゃるのですか、大王。タケル様も、大王に乗せられてはいけませぬ。もうすぐ、人の親になろうという方が」
え!? っと、レーテーもタケルも振り返った。大王もキョトンとした顔をしている。
「そうなのでございましょう? フタヂノイリヒメ殿のこと、お屋敷の方はひた隠しにしていらっしゃいますが、時折采女を遣わせて様子を窺っておりました。そこから察するに、フタヂ殿はご懐妊なされておいででしょう?」
それを聞いた大王は、驚きとも恐怖ともつかぬ表情をして、
「まことなのか?」と、タケルに聞いた。
「ええ、まあ......」
と、タケルは忌々しそうに答えてから、ヤサカノイリビメに言った。
「そこまでご存知なら、フタヂが気鬱の病であることも?」
「ええ、察しておりました。ですから私は心配をしていたのです。無事にご出産できるかどうかと......」
そこで、レーテーが口を開いた。「それは問題ございません。そのために私はこちらへ参ったのです」
レーテーは大王の方に向き直すと、跪いて見せた。
「私は天照さまにお仕えする祈祷師であり奇術師。私の力をもってすれば、万事うまく行きます。なにしろお生まれになる子は、タケルの御子である前に、偉大なる大王さまの血を引く御子なのですから」
事情を知らない者には「大王の孫」という意味に取れるが、知っているものにはまさしく「大王の子」だということが分かる。それを今ここでレーテーが口にしたのは、大王に対する牽制だった。
それが分かって、大王は険しい表情をした。
「良かろう。無事に御子が生まれてくるよう、そなたが取り計らうが良い」
大王はそう言うと、これ以上自分に不利な話が出ないように、その場を退出するのだった。
大王がいなくなったことで、レーテー達は帰ることになった。王宮の表門までヤサカノイリビメとワカタラシヒコが送ってくれた。すると、そこで今まさに門から入ろうとする青年がタケルに声をかけた。
「オグナ様ではいらっしゃいませんか」
「?......あ、オビトか?」
オビトと呼ばれた青年は、傍まで来ると恭しくお辞儀をした。
「ご無沙汰をいたしております。この度は無事にお役目を果たされたこと、お喜び申し上げます」
「ありがとう、オビト......髪形が代わっていたから、分からなかったよ。わたしがいない間に成人の儀式を挙げたんだな」
「はい。そして、名も改めましてございます。今は亡き父の名を継いで、武内宿禰(たけしうちのすくね)を名乗っております」
「そうか、父上の名を継いだのか......わたしも改名したんだ」
「噂に聞いております。今はヤマトタケル様とおっしゃるのでしたね。......察するに、こちらが伴われて御帰京されたという方でいらっしゃいますか?」
「ああ、紹介するよ」と、ムタケルはレーテーの方を向いた。
「わたしの嬪のオトタチバナヒメだ。オトタチバナ、彼は代々我が王家に仕えてくれている武内家の長男で、わたしの昔馴染みだ」
「まあ、左様でございますか......」と、レーテーは答えて、「どうぞお見知りおきを、スクネ殿。私の故郷の挨拶をしてもいいかしら?」
レーテーはそう言って、スクネと握手をした。
「ほう、これは初めて知る挨拶の作法ですな。御内儀(ごないぎ。貴人の妻のこと)は外国(「とっくに」と読む)の方でいらっしゃいますか」
「ああ、あまり詳しくは話せないのだが」
と、タケルが答えて、「それじゃ、わたし達はちょっと急ぐから......失礼いたします、ヤサカノイリビメ様。ワカタラシヒコも、またな」
タケルはレーテーを連れて、半ば逃げるようにその場を後にした。
王宮からかなり離れると、タケルは口を開いた。
「急に変なことするなよ。あんな挨拶、今までやったこともなかったのに」
「ごめんなさい」と、レーテーは笑って見せた。「でも、どうしても彼に触れて、記憶を見たかったものだから」
「どうゆうこと?」
「先ず大王がね――王冠を乗せてあげる時に見えたんだけど、あなたの暗殺を企てていたのよ」
「わたしの?」
「ええ。あなたを、盗賊に襲われた風に装って、伊勢からここまでに来る間のどこかで」
「それじゃ、君の力で水の中を通って来たのは正解だったんだ」
「そう。だから大王は、あなたが無事に帰郷したことに驚いていたわ。どうして企てが失敗したのか、まったく分からなくて」
「なるほど......それで、その暗殺の指示を受けたのがオビト......いや、スクネだったのか」
「ええ。でも彼は、初めから指示通り動くつもりはなくて、何らかの方法で企てが失敗したことにして、あなたを助けるつもりだったわ」
「それを聞いて安心したよ。オビトはそんなことが出来る様な人間じゃないから」
「でも、彼はどちらかというと、あなたよりヤサカノイリビメ寄りの人よ。次の大王はワカタラシヒコをと考えて、ヤサカノイリビメと親しくしてるわ」
「それでいいんだよ。わたしだって大王になんてなりたくない。れっきとした王子のワカタラシヒコがいるんだ。ゆくゆくはわたしも、大王となったワカタラシヒコを支えて行ける立場になりたいと思ってる」
「そう。あなたがそう思ってるのなら、スクネはあなたにとって敵にはならないと思うわ。それにしても......こう言ってはなんだけど、あの大王は本当に最低な男ね」
「そもそも、父上はどうしてわたしを暗殺しようとしたの?」
「フタヂ様を自分だけのものにするためよ。夫を失った王女は王宮に帰って来るしかないって、そう思って。しかもフタヂ様は今、正気ではないから。いいように操れると思ったのよ」
「つくづく下衆だな!」と、タケルは吐き捨てるように言った。
「それから......」と、レーテーは言いにくそうにしたが、
「いいよ、言ってくれ」とタケルに促されて、口を開いた。
「あなたにはもう、利用価値がないと思ったのよ。ほら、オオウスに襲われても、子供が出来なかったから......」
「なるほど」と、タケルは苦笑いを浮かべた。「わたしのことを石女(うめずめ。子供を産めない女性に対する蔑称)と思ったか。子孫を残せないわたしは、ワカタラシヒコがいる時点で既に邪魔な存在だと。......人を人とも思っていないのだな、あの下衆は――そんな男の、血を引いているのか、わたしは。生まれてくる子も......」
「そんな風に卑下しないで。人格を形成するのは血ではないわ。育ってきた環境よ。あなたはとてもいい人よ。だから、私はあなたを好きになったんですもの。種族を超えて......」
「......ああ、そうだね」
本当なら、ここでキスの一つもしたいところなのだが、まだ王宮に近いこともあって人通りもあり、二人は見つめ合うだけで満足した。
そんな時だった。風に乗って芳しい香りが漂ってきたのは。
「あれ? これって......あ、やっぱり」
レーテーは香りを放っているそれの傍に駆け寄った。
四角く囲いが組まれているその中央に、一本の樹が立っていた。それは橘の樹に間違いなかった。が......。
「それは"非時香菓(ときじくのかぐのみ)"だ」
「え? 橘じゃないの?」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2013/09/13 09:17:49
icon
白鳥伝説異聞・14
「先ずは口の堅い産婆を探さないといけないのだけど......」
レーテーが険しい表情で言った。それが一番難しそうだと思っていたのだが、
「それならば心配はございません」と、ミヤベが言った。「この屋敷に仕える五人の采女すべて、産婆の心得がございます」
「え!? 五人とも!?」
これは予想外だった。
「はい、大王のご命令で。いつかタケル様が御子をお生みになることがあれば、秘密裏に私共が行えるようにと、定期的に交代で産婆のもとへ修行に行っております」
「用意周到なのね......」
結局のところ、タケルを男児として育てるにしても、跡継ぎを儲けるためにはタケル自身に子供を産んでもらわなくては血筋が絶えてしまう。もしかすると、タケルをオオウスに襲わせたのは大王なのではないだろうか。その同時刻、大王がフタヂに襲い掛かっていることからも考えて......。
「それなら、私の計画に何の支障もありません。タケルが女であることを知られないようにするのも勿論ですが、何よりも、生まれてきた子が......」
レーテーがそこまで言いかけた時、外から声がした。
「申し! どなたか、おられませぬか! 申し!」
王宮に仕える采女だった。大王からの使いで、木簡(もっかん)に書かれた文(ふみ。手紙)を持ってきたのである。
ミヤベが表へ出て受け取り、タケルに渡した。
難しい漢字で書いてあるのを、タケルはレーテーに分かるように説明した。
「帰ってきているのなら顔を見せろ、だとさ」
「それは、ごもっともね......」
と、レーテーは言った。普通の親なら、子供が帰ってきているのなら顔を見たいと思うものである。しかし、皆の話を聞いただけだと、大王はタケルにとって普通の父親には思えない。
「おもてにまだ王宮の采女は待たせてあるのか? では、明日参上つかまつると、伝えてきてくれ」
タケルはそう言って、木簡をミヤベに渡した。
「畏まりました......お一人で参られますか?」
「ああ......」
タケルとフタヂが襲われたのは、まさに王宮に上がった時である。一人で行くのは危ないと、ミヤベが思うのも無理はない。
「そうだな。ミヤベ、付いてきてくれるか?」
「だったら」と、レーテーは言った。「私が行くわ!」
「駄目だ!」と、咄嗟にタケルが言った。「君が襲われたらどうするの!」
「大丈夫よ、私なら。私が普通の人間じゃないの、分かってるでしょ?」
「あっ!?......そうでした」
ついついレーテーが女神であることを忘れてしまうタケルだった。
「では、オトタチバナ様もご一緒ということで......なんと申し上げたら良いでしょうか?」
と、ミヤベが言うと、
「なんと、とは?」と、タケルが聞き返す。
「オトタチバナ様のお立場です。タケル様の想い人、というだけのお立場では、王宮にはお上がりになれないかと」
「ああ、そうだな。......オトタチバナ、君さえよければ、わたしの嬪(ひん)にならないか?」
「ひん???」
初めて聞く単語に、レーテーの頭の中で?マークが躍った。
「王族出身は"妃"って言うけど、豪族出身は"嬪"って言うんだ」
「それって......つまり、妻?」
まさか、こんなタイミングでプロポーズ?......と、思ったが。とりあえずは大王の手前、そうゆうことにしよう、とタケルは言っているのだった。
王宮へはお昼ごろに参内した。
初めて見たタケルの正装があまりにも格好良くて、レーテーは見とれてしまったが、それはタケルの方もだった。
「王族出身の姫君と言っても過言じゃないぐらい、綺麗だよ」
「ありがとう。こうゆう装飾品も付けるのね。全部、フタヂ様の物?」
と、最後の方はミヤベに聞くと、
「とんでもございません。フタヂ様の物を一つでも身に着けていては、その場限りの"嬪"を演じていると、大王に見破られてしまいます」
「じゃあこれ、全部買い揃えたの? 一晩で?」
髪飾り、腕輪、首飾り......どれも煌びやかで豪華な物である。これらを一晩で用意するなど......と、レーテーはびっくりしていたが、ミヤベはさらっと答えた。
「それぐらいのことが出来なければ、タケル様の采女は務まりませぬ」
「ああ、そうなのね......」
秘密を守るって大変なんだな、とレーテーは改めて思った。
実際に王宮に上がると、王宮に仕える者たちが皆、レーテー――オトタチバナヒメの美しさに目を奪われていた。美男児であるタケルと並び立つと、それこそ、この世のものとは思われないほどだった。
二人は謁見の間に通された。
そこへ、一人の少年が入って来た。
「兄君!」と、手を振りながら走って来た少年を、タケルはしっかりと抱き留めた。
「ワカタラシヒコ、元気そうだな」
「兄君も。御無事でなによりです」
そう言っている間に、奥から美しい女性が現れた。レーテーと負けぬ劣らぬの装飾品を付けているところを見ると、大王の妃のようだった。
「お帰りなされませ、オグナ様――いえ、今はタケル様とおっしゃるのでしたね」
「八坂入媛(やさかのいりびめ)様。帰郷のご挨拶が遅れて、申し訳ございませんでした」
タケルはそう言って、ワカタラシヒコを離すと、レーテーを一歩前に出させた。
「紹介します。わたしの嬪で、オトタチバナヒメでございます。オトタチバナ、こちらは父君の大后(おおきさき。大王の妻の中でも最高位)で、ヤサカノイリビメ様。先々代の大王のお孫様にあたられる。つまり、父とはいとこ同士になる」
要するに、生まれも育ちも王族の姫君ということだ。道理で立ち居振る舞いが上品なわけである。
「そして、こちらがヤサカノイリビメ様の御子さまで、若帯日子(わかたらしひこ)。わたしの弟だ」
「初めまして、オトタチバナ様」
ワカタラシヒコは元気にあいさつして見せた。まだ5歳ぐらいで可愛い盛りである。
「初めまして、ワカタラシヒコ様」と、レーテーはワカタラシヒコに微笑んでから、ヤサカノイリビメに恭しく頭を下げた。
「初めてお目にかかります、オトタチバナでございます」
「こちらこそ、初めまして......嬪ということですが、御出身はどちらなのですか?」
ヤサカノイリビメが聞くと、レーテーは、
「あいにく、天照さまに仕える祈祷師である私は、自分の出生を明かすことができませぬ。ご容赦下さりませ」と、ごまかした。
「まあ、身分を明かせぬとは......よもや、神の血を引いておいでか?」
神に仕える特別な者ならば――と、ヤサカノイリビメは考えたが、その答えもレーテーは微笑むことで制した。
すると......、
「ふん。奇妙な女を妻にしたものだな、オグナよ」
奥から豪華に着飾った大男が出てきた。
その顔を見た途端、レーテーの背中に冷たい物が走った――フタヂの記憶を垣間見た時に伝わってきた、あの恐怖感が蘇って来たのである。
『間違いない。フタヂ様を辱めたのは、この男......』
倭の大王・大足彦忍代別(おおたらしひこおしろわけ)――後に景行天皇と称される人物である。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-