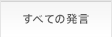サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: エリスさん
2014年02月28日 10時17分26秒
icon
白鳥伝説異聞・20 その2
「そなたの記憶を見せなさい。もっと、深層心理まで!」
レーテーは大王の頭を両手で鷲掴みにすると、ラベンダーの体香を最大にして、それによって引き起こされる眠気で大王を抵抗できなくした。タケルはそれを察して、ヤサカノイリビメを連れてその場から遠ざかった。
レーテーは大王の記憶を、タケルが生まれた頃まで遡った――そして見えたものは、タケルの母・播磨稲日大郎女(はりまのいなびのおおいらつめ)を失った悲しみだった。
『大姫、何故死んだのだ。おまえと引き換えになるぐらいなら、子供などいらぬものを......』
本当に愛しているのはフタヂノイリヒメかもしれないが、タケルの母・大郎女(大王は大姫と呼んでいた)のことも、フタヂのことを忘れていられるぐらい愛していたのだろう。その大郎女が死んでしまい......大王の心に一瞬、邪心が浮かんだ。
『大姫の産んだ子なら、大姫そっくりに育つのか? そうなれば......』
その邪心は良心によって掻き消されたが、いつまたその邪心が沸き起こるかと、大王は恐れた......。
――レーテーは、手を離すと、言った。
「だから、タケルを男として育てたと......?」
レーテーがつぶやくと、タケルは歩み寄りながら聞いた。「何を見たのだ?」
「あなたの母君を愛するあまり、あなたを母君の身代わりにしようと思ったことを」
「母の身代わり?」
「つまり、あなたを性の対象として......」
タケルの体に鳥肌が立つとほぼ同時に、ヤサカノイリビメは言った。「思っただけです! そうなってはいけないと、父親としての理性で抑えて、でもいつまで抑えられるか分からなかったから、タケル様を男子として......」
「理由は何であれ、タケルから本来の姿を奪うなど、身勝手すぎます!」
レーテーは言うと、大王を見据えた。
「そもそも父親が、我が血を引く娘を性の対象として見ること自体が間違っているのです。そんな奴は人間じゃない、ケダモノよ! そんなことを理由にして、タケルの女性としての総てを否定するなんて......そんなことを理由に、タケルを自分から遠ざけるために熊襲討伐に行かせたり、帰郷途中で盗賊に襲わせて殺そうとしたりするなんて。なにが父親としての理性ですか! 理性が効かないと分かっているのなら、自らの命を絶つべきだったのよ!! 子供を親の犠牲にしないで!!」
「もういい!」
そう言ったのは、タケルだった。「もういい......やめて、レーテー......」
タケルは泣いていた――怒りよりも、悲しみの方が強くて、男を演じることができなかった。
「もう何も聞きたくない......」
「タケル......」
レーテーはタケルの方へ行き、彼女を抱きしめた。
「帰ろう、レーテー。もうこんなところに居たくない」
「ええ、そうね」
レーテーはタケルを支えたまま歩きだし、その時、赤ん坊が声を上げたので立ち止まった。
「そう、この子のことを忘れていたわね」
レーテーはそう言うとタケルから手を離して、赤ん坊を抱き上げに行った。
「フタヂノイリヒメはこの子を産んだことを忘れています。私の力で、この子はタケルの腹から産まれたと思い込んでいます。その上で、世間には自分が産んだことにして、ヤマトタケルノミコトの第一子として自分が立派に育てて見せると、そう言っています。ですから、あなた方もそのつもりで。決して真実を口にしてはいけませんよ」
「承知いたしました、姫神様」と、ヤサカノイリビメは言った。「決して口外いたしません。そうですよね?」
最後の方は大王に言った言葉だった。大王も黙ってうなずいた。
「頼みましたよ......私のことも、ね?」
と、最後にレーテーはにっこりと笑って見せた。
帰り道、二人はほとんど黙っていた。時折、ワカタケルと名付けられた赤ん坊をあやすぐらいで......何をしゃべっていいか分からなかった。
それでも、まったく人通りがない道まで来ると、ようやくタケルが口を開いた。
「理由が分かって良かったよ」
タケルは深いため息を付いた。「母上を愛しすぎていたから......その理由は、少なからずわたしを納得させた」
「そんな......」
「神の目から見たら、とんでもなく愚かに見えるかもしれないけど、わたしは理解できるんだ。わたしだって、フタヂの代わりにタチバナヒメを......」
「次元が違うわ! あの男が身代わりにしようとしたのは、血のつながった......」
「身代わりを求めたという点では同じことだよ......いいんだ、わたしが父上を理解できれば、それで。それに、結局父上はわたしを身代わりにしなかったんだから。その代わりわたしを男に仕立てた。その方が、まだいい」
「......タケルがそれでいいのなら、私ももう何も言わないわ」
レーテーとしてもこれ以上タケルの心を掻き乱したいわけではない。タケルの心に平安がもたらされるのなら、もう何でもよかった。
二人が屋敷に着くと、タガタが出迎えてくれた。
「フタヂ様の診察に、オトタチバナ様のお母上と名乗る方がお見えになってます」
「私の母?」
「ええ。オトタチバナ様にそっくりでいらっしゃるので、私たちも信用してお通しいたしました」
「そう......どこにいるの?」
「フタヂ様のお部屋です」
レーテーとタケルは早速行ってみた。
「母上って、どっち?」
と、タケルは聞いた。レーテーから実の母(エリス)と二人目の母(エイレイテュイア)のことを聞いていたからである。
「可能性として、二人目の......」
言いかけているうちにフタヂの部屋に着いて、中からフタヂの楽しげな声が聞こえた。
「お母様は大変物知りでいらっしゃいますね」
「恐れ入ります、お后様」
この声を聞いて、レーテーは確信を得た。
「フタヂ様! オトタチバナです。タケルも居ます。お邪魔してよろしいですか?」
仕切り戸の前から声を掛けると、中から「どうぞ、入って!」というフタヂの声が戻ってきた。
二人が中に入ると、寝床で身を起こしているフタヂの隣に、40代前後の女性が座っていた。
「久しぶりね」
そう挨拶した女性は、オトタチバナヒメをそのまま老けさせたような倭人に化けてはいたが、エイレイテュイアに間違いなかった。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2014年02月28日 10時16分15秒
icon
白鳥伝説異聞・20 その1
「ワカタケル......ですか」と、タケルは言った。「わたしの名から一字を取る、ということは、わたしの御子として育ててもいい、ということですね?」
すると大王は苦笑いを浮かべた。「何を言っている。そなたの子であろうが」
「わたしの子でないことは、あなたが一番ご存知のことではございませぬか」
「何を訳の分からないことを申しておる」
「今更ごまかさないでください。そもそも、わたしとフタヂは女同士なのですよ」
タケルの言葉に、フンッと大王は馬鹿にした笑いを浮かべた。
「それを......そなたが女であると言う秘密を口にしてはならぬものを、何故そなたは簡単に口にするのだ」
「ここにはわたし達以外誰もいないのだから、構わないではありませんか」
「そなたが秘密を漏らすかもしれぬと思ったからこそ、今日は人払いをしておるのだ」
「秘密をばらされて困るのはあなたですからね」
「先刻からなんだ、その態度は! 親に向かって!!」
「親なら!」
何をやってもいいのか! とタケルが怒鳴ろうとしたところを、レーテーが制して、代わりに言った。(赤ん坊はその前に椅子の上に寝かしつけた)
「女同士の夫婦であるお二人の間に子供が出来たのなら、他に本当の父親がいるはずです」
「ほう?」と、大王は感心したように言った。「そなたもタケルが女であることを知っていたのか。では、嬪というのは本当のことだったのか?」
下卑た笑いが気持ち悪かったが、レーテーをそんな大王に軽蔑の眼差しを送りながら言った。
「嬪になったというのは嘘ですが、私がタケルと恋人同士なのは本当です。飽くまで対等な立場で、神も人間もなく......」
「......神、だと?」
「そう、私は......」
レーテーは、オトタチバナの姿から本来の姿に戻って見せた。
「私はオリュンポスの女神エリスが長子・レーテー。人の記憶を読みとり、また書き換える能力を持っています」
レーテーの姿を見て、流石に大王も驚いていた。異国の人種も、ましてや神も初めて見たのである。当然と言えた。
それには構わずにレーテーは続けた。
「そなたの悪行は、フタヂノイリヒメの記憶と、そして先日そなたの額に触れた時に垣間見した記憶とで分かっている。よって、フタヂノイリヒメが産んだ子がそなたの子であることも!」
よもや言い逃れなど出来ようはずもない。大王が言葉も出なくなっていると、奥の間がゆっくりと開いて、誰かが入って来た。
レーテーは急いでオトタチバナの姿に戻ったが、戻っている最中の姿をその人物に見られてしまった――ヤサカノイリビメだった。
「恐れ入ります、外国(とっくに)の姫神様。図らずもそのお姿を拝謁してしまいました。お許しください」
「いいえ、あなたなら構いません」と、レーテーは言った。「あなたは口の堅い人だと思います。それに、今から話すことはあなたにも協力してもらうことがあるかもしれないわ」
「お信じ下さって恐悦にございます」
ヤサカノイリビメは深々と頭を下げると、少々失礼します、と言いつつ大王の方へ行った。
ヤサカノイリビメは大きく手を振り上げると、大王の頬を打った。
大王がびっくりすると、尚も一発、もう一発と、何度も何度も大王の頬を平手で打ち、しまいには拳で彼の肩や胸を殴った、泣きながら。
「どうして! どうして私という者がおりながら、異母妹にまで手をお出しになるのです!!」
言いながら泣き崩れても、ヤサカノイリビメはなじるのを止めなかった。
「あなたが私のことを愛して下さっていないのは、初めから気付いていました。それでも私は妻としてあなたに尽くして、あなたが私に望む物はすべて差し上げてきましたものを......まだ足りないと申すのですか......」
ヤサカノイリビメのそんな姿を見ていられなくて、タケルは彼女を助け起こそうと近寄った。
「ヤサカ様、どうかもう、その辺で......」
タケルの手を取りながらヤサカノイリビメはタケルを見上げた。
「本当に、女性(にょしょう)なのですか?」
「......はい」
タケルは手に取ったヤサカノイリビメの手を、自身の胸に触れさせた。
「この通り......」
「ああ、道理で、殿御にしてはお美しい御顔立ちをしていると思っておりました。きっとお母様に似ておいでなのだと......そうでしたか。これで、すべて合点がいきました」
ヤサカノイリビメは自分で立ち上がり、タケルに言った。
「タケル様、あなたが男子として育てられたのは、すべてそのお母様似の御美しさ故です」
「え?」
「どうゆうことですか?」と、レーテーも聞いた。
「大王は恐れていたのです。播磨の......タケル様のお母様を失って、その寂しさゆえに......」
すると咄嗟に大王は「やめよ!!」と怒鳴った。
「私はいつも聞かされているのです! あなたが眠りながら語る、うわ言を!」
「黙れ!」
「黙るのはそなたです!」と、レーテーが言い放った。「まだ隠していることがあるようね」
レーテーは両手を大王の頭に伸ばした。
「何をする......」
「そなたの記憶を見せなさい。もっと、深層心理まで!」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-