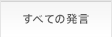サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: エリスさん
2012/02/24 11:26:50
icon
「ようこそ!BFWへ・3」
「さてと、それじゃ……」
東の街の女王・北野真理子は言った。「手始めに私たちのコラボといきますか?」
「五大女王で?」
と、南東の街の女王・流田恵莉は言った。「いいんじゃない。私は歌えばいいのかな?」
「もちろんよ、エリー。あなたの美声を聞かせて」
「私は無理よ、マリコ」と南の街の女王・武神莉菜は言った。「私の芸術は舞踊だけなんですもの、あなたたちのロックには合わせられないわ」
「それじゃ、リナは見学するとして……裏方のみなさん、楽器用意して! ドラムスは3セットね!」
マリコのその言葉を聞いて、ん? と北の街の女王・佐保山郁は思った。
「3セットって、マリコ! 私も勘定に入っているの!?」
「当然でしょ。あなたが出来る楽器は?」
「ドラムスとパーカッションでしたけど、それは過去のことよ! 私は中学生の時に右手首故障して、それ以来、打楽器全般から手を引いたって――御祖の実体験そのままの設定があるから、もう出来ないのよ!」
「大丈夫よ、ここは想像の世界なのだから、今だけやってまた手首を痛めても、私たちが治してあげるわ」
「いえ、ですから、そういう設定があるだけで、物語の中で実際に私がドラムスを叩いてるシーンはないので、本当にできるかどうかなんて分からないんです!」
「あなたはどう思う? アーサ」と、真理子は北東の街の女王・水島有佐の方を向いた。「あなたはカール(郁)の親友だから、今までの彼女を見てきて、出来るかどうか判断できるのじゃない? 同じドラマーとして」
「いやまァ……」と有佐は言った。「カールは、リズム感はありますけど……」
「はい、決定」
と真理子が手を叩いたので、郁は莉菜にすがりついた。
「リナァ〜〜! マリコがいじめるゥ〜〜!」
「はいはい、くじけちゃダメよ、カール」と莉菜は郁の背を撫でた。「もう、マリコったら。無茶ぶりはやめてあげて。いくらカールが、忘れ去られた私たちと違って、今でも他の作品にゲスト出演しているからって、僻(ひが)むなんていけないわ」
すると真理子は「フンッ」と向こうを向いてしまった。
「ねえ、マリコ。久しぶりにJunoの演奏を聴きたいわ。あなたのバンドのメンバー、来てるのでしょ? やってよ」
と、莉菜は郁から離れて、真理子に歩み寄りながら言った。「エリーとアーサとカールは、芸術学院シリーズのキャラクターでもあるのだから、そっちのメンバーで何かやって見せて」
「ああ、だったら!」と恵莉が言った。「あれやりましょ。“キャバレー”の第5場。ステージでショーを見せるシーン。私は出演してなかったけど、あの歌なら歌えるわよ。演奏はアーサのBad Boys Clubで」
すると郁は大きく頷いた。
「それ行こう! 絶対それがいい! もう、それで決まり!」
「それじゃ、俺たちも出番ですね!」と、芸術の町の町長・草薙建が手を挙げた。「住民総出でいきますか!」
「そういうことだから」と莉菜は真理子の肩を叩いた。「よろしくね、マリコ」
真理子は気まずそうだったが、
「まあ……リナがJunoを見たいと言うなら……」
「うん、お願いね」
真理子はその場から離れ、自分のバンドのメンバーを呼びに行った。
Junoが演奏している間、芸術学院シリーズの面々は、舞台裏で自分たちのステージの準備を始めた。
「竹林三姉妹も手伝ってくれるだろ?」と建は三つ子の姉妹に声を掛けた。「あなた達が入学する前に上演した舞台だから、知らないだろうけど」
「いいえ」と長女の竹林愛美子(たけばやし えみこ)は言った。「私たち、客として見に来てましたから、知ってますよ」
「あっ、そうなんだ。そりゃ好都合。実は、えっちゃん(愛美子)にはアヤ姉ちゃんの代役をやってもらいたいんだよな」
「え!? 北上先輩の!?」
「そう。姉ちゃん、別の用事で今いないんだ」
「ええ、伺ってますが……北上先輩の役って、あの真っ赤なチャイナドレスで踊ってた、佐保山先輩の相手役でしたよね?」
「うん。出番多いけど頼むよ」
「いや、出番が多いのはいいんですけど……確か、あの役って……佐保山先輩に抱き留められて、スリットの中に手を入れられますよね……」
「ああ、入れてるね」
と、建が言った時、ちょうど郁もやってきた。
「入れるだけじゃなくて、撫でてるけど」
そこで、愛美子の彼氏である榊田祐佐(さかきだ ゆうすけ)は「え!?」と驚いた。
「あの、スリットって……チャイナドレスの太ももの割れ目のことですか?」
「そうよ」と郁は言った。「それ以外にどこがあるの?」
「つまり、先輩が撫でているのは、おしりですか?」
「そうゆうこと」と建が言った。「いやあ、あの時のアヤ姉ちゃんは、演技でやってるとは言え、色っぽいよがり方してましたよねェ」
「あら、演技とは失礼ね。本当に感じさせてたのよ、私のテクニックで……」
と郁が言った時、祐佐は愛美子の前に立ちはだかった。
「絶対だめです! えっちゃんの体に厭らしいことなんかさせません!!!!」
「あらあら」と郁は苦笑いをした。「女優を目指す えっちゃんに、そうゆう制約を強いるのはどうなのかしら?」
「えっ……ええっと……」
祐佐だけではなく、愛美子も頭をひねって悩みだしてしまったので、郁はクスクスッと笑い出した。
「いいわ。じゃあ今回は、腰を抱くだけにしてあげる。それならいいでしょ?」
「あっはい……いいえ!」と愛美子は言った。「本来の振り通りにしてください。私、やります! 女優ですから!」
「そう? じゃあ、よろしくね。――タケル、振り付け指導してあげて」
「はい、カール姉さん」
郁は、後は後輩たちに任せて、控室へ行った。そこには、先ほどまで郁子が横になって休んでいた座布団と、膝掛けが、きちんと揃えられて置かれていた。
テーブルに飲みかけのペットボトルが置いてある……アールグレイの紅茶ということは、間違いなく郁子の飲み残し。
郁はそれを手に取って、蓋を外すと一気に飲み干した。
「アヤ、大丈夫かしら……」
いろいろな意味で心配する郁だった。
郁子が〈神々の御座シリーズ・人間界の町〉に着くと、そこは高い鉄筋の城壁で囲まれていた。
「すごいね……」と、車を運転してきてくれた祥が言った。「これが一瞬のうちに現れたって、東の街さまは言ってたけど」
「ここの住人の皆さんは、ただ者じゃないから……」
郁子は城壁を見渡して、ようやく入口を見つけた。「たぶん、あそこだわ」
すりガラスの横開きのドアがあった。その前に立つと自動ドアになっており、二人は簡単に中に入ることができた。
中は銀行のATMを思わせる作りになっていた。暗証番号を打ち込むコンピューターが一台置かれているだけである。郁子がその前に立つと、自動的にコンピューターの電源が付いた。
〔ログインパスワードを入力してください〕
画面にそう表示されたので、郁子は自分のパスワードを入力した。
〔inui-01-ayako-kitagami-asura〕
すると、画面の上の壁が開いて、マイクが出てきた。
「え?」
と郁子が戸惑っていると、画面に次のメッセージが表示された。
〔額田王の長歌を暗唱してください〕
「はァ? なに、これ?」
「ちょっと待て、もしかして……」
祥は画面の「ひとつ前に戻る」をタッチして、自分のパスワードを入力した。
〔inui-02-shou-takagi-kabuki〕
すると今度は、壁からビデオカメラが出てきた。
〔吉野山の静御前を舞ってください〕
「こんな狭いところで舞えるか!」
「これって、つまり……」
パスワードと一緒に、その本人の得意技を披露してもらって、本人に間違いないか確認しているようである。
「これって、カメラの前で審査してるのって、もしかしなくても乃木さんか?」
「吉野山の静御前の舞を判断できる人ったら、この町じゃ乃木さんだけよね。あの方も元歌舞伎役者なんでしょ?」
「そう、僕と一緒……モデルが同じ人だからな」
「どうする? あなたがやる?」
「勘弁してくれよ……」
「じゃあ、私がやるしかないわね」
郁子は画面をひとつ前に戻して、自分のパスワードを入力し、マイクを壁から出した。
「冬ごもり 春さり来れば
鳴かざりし 鳥も来鳴きぬ
咲かざりし 花も咲けども
山を茂み 入りても取らず
草深み 取りても見ず
秋山の 木の葉を見ては
黄葉(もみじ)をば 取りてぞしのぶ
青きをば 置きてぞ歎く
そこし恨めし
秋山ぞわれは」
郁子が暗唱し終わると、目の前のコンピューターが床の中へ沈んで、通路が開いた。通路の奥にドアが見える。
「合格――ってことかしら?」
「よくぞ一言も間違えずに……うちの奥さんの才女ぶりには惚れ惚れするね」
「ありがとう、あなた。行きましょ」
二人は通路の奥へと歩いて行った。icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/20 17:35:32
icon
「ようこそ!BFWへ・2」
郁子が御祖の住む居城に着いたときには、他の町の住人達がもう行動を起こしていた。
「あっ、アヤ姉ちゃん!」
草薙建(くさなぎ たける)――「芸術の町」の町長。出演作品は「芸術学院シリーズ 俺たちに明日はある?」など多数。郁子とは義姉妹の盃を交わしている。男っぽく育てられているが、歴とした女性。
「タケル、もう来てたの?」
今更ながら、北上郁子(きたがみ あやこ)――「乾の町」の町長。出演作品は「芸術学院シリーズ 狂おしく虚しく」「箱庭」など多数。
「〈雪原の桜花の町〉にはうちの亭主と紅藤ちゃんの旦那さんが居たもんで、そっちから直で救助要請が来たんだ。〈雪原〜〉の住人さん、大方蘇生させたよ」
「そう、良かった……あと何人残ってるの?」
すると、劇場のドアが開いて、三人の人物が出てきた。
「あと三人です、アヤさん」
紅藤沙耶(くどう さや)――「芸術の町」の住人。出演作品は「箱庭」。郁子の再従姉妹にあたる。
「〈雪原〜〉はまだ出来たばかりの町で、そもそも住人も十人ほどしかいないんだ」
黒田龍弥(くろだ たつや)――「芸術の町」の住人、草薙建の夫。出演作は「芸術学院シリーズ 俺たちに明日はある?」など多数。
「そのうち二人は、俺と黒田さんでしたからね」
崇原喬志(そねはら たかし)――「芸術の町」の住人、紅藤沙耶の夫。出演作品は「箱庭」
「物語がリンクしていて、ゲスト出演って奴」と黒田は言った。「おかげで巻き込まれたが」
「それで、蘇生できない三人と言うのは?」
郁子はそう言いながら、劇場の中に入って行った。
「主人公の持田沙雪と、その恋人の二人……」
と建が言うと、二人? と郁子は聞き返した。
「このBellers Formation Worldで、主人公に恋人が二人いるなんて、初の設定ね。同時期に付き合ってたわけではないの?」
「同時期ですよ」と崇原は言った。「ちょっと複雑な設定なんですよ」
舞台の傍――最前列の客席に、その三人は座らせられていた。真ん中の三十代前半の女が主人公であり〈雪原の桜花の町〉の町長・持田沙雪。その右隣にいるのは十四、五歳に見える少年で、左隣にいるのは、十八歳ぐらいの少女だった。
「持田沙雪はバイ・セクシャルってことね。その設定ならありがちだわ」
郁子が言うと、黒田が説明した。
「正確に言うと、本命はこの彼――朝井洋伸(あさい ひろのぶ)なんだ。持田は大人の男が駄目で、男は少年しか愛せない。だから、恋人が大人に成長したら嫌いになってしまうのではないかと恐れて、なかなか男と付き合えないんだ。だから、洋伸君にも告白できない――彼は理想的な相手だと言うのに」
「理想的? 彼だっていつかは大人になるでしょ?」
と郁子が聞くと、黒田は目の前で人差し指を左右に振って見せた。(念のために説明すると、「芸術学院シリーズ」で郁子と黒田はライバル関係にある)
「彼はこう見えて二十歳だよ」
「ええ!?」
どう見ても中学生にしか見えない。
「俺とまた違った設定なんですよ」と崇原が言った。「俺は、死んだ妹に気兼ねして、自分から歳を取らないように暗示をかけているから、実年齢より若く見えますが(「箱庭」を参照)、彼は幼いころに事故にあって、成長が止まってしまったという設定なんです」
「ああ……いるよね、そうゆう人。そうなんだ……」
郁子が感心していると、黒田がまた説明を始めた。
「でも、本当に成長が止まったままでいる保証はない。もしかしたら大人になってしまうかもしれない。だから、持田はこっちの彼女――庚 結花(かのえ ゆか)と付き合っているんだ」
「本命の代わりに?」
「結花さんもそれは承知で付き合っているんだよ。健気な子でね」
「そう……それより、あなた先刻から町長を呼び捨てで呼んでるけど、どうゆう立場なの?」
「俺と崇原さんは持田の会社の上司なんだ」
「ああ、海源書房のね」
そこで高木祥が口を挟んだ。「説明はこれぐらいでいいだろう? アヤ。そろそろ始めよう」
「そうね……着替えて来るわ。演奏は誰がやってくれるの?」
すると舞台のそでから十二単の女性が現れた。
「私どもが勤めさせていただきまする、乾の町さま」
藤原刀自子(ふじわらのとじこ)、またの名を彩の典侍(あやのすけ)――「平安の町」の町長。出演作品は「雅シリーズ 藤之木慕情」ほか多数。
「彩の典侍さんの演奏なら心強いわ」
過去にも御祖の君が重病などで執筆活動を止めてしまうと、現在執筆中の町の住人が仮死状態になることがあった。その度に、すでに物語が完結し、自由気ままに生活している他の町の住人達が協力して、「芸術魂(アーティストパワー)」を分け与えて蘇生させていた。その「芸術魂」を分け与える方法は、いとも簡単である。それぞれが得意としている芸術を披露すればいいのである。
郁子と祥が得意としているのは日本舞踊――夫婦舞である。
二人は白装束に着替えて、舞台の上に上がった。
「平安の町」の雅楽師たちが演奏を始める――郁子と祥は、誰もがうっとりとするような舞を舞い始めた……。
「沙雪さん! しっかりして! ねえ、沙雪さん!」
二人の舞で目が覚めたのは、結花だけだった。
郁子はとうとう息を切らして、舞台の上で膝を突いた――かれこれ三十分は舞っていたのである。
「なぜ……何故、この二人だけ……」
舞台袖の「平安の町」の雅楽師たちも、もう限界に来ていた。当然、祥もである。
『やっぱり、御祖の君がお出ましにならないと……御祖が閉じ籠られた原因に、この二人は直結しているのかもしれない』
郁子がそう思っていると、劇場に五人の女性が入ってきた。そのうちの一人が、郁子が膝を突いているのを見て、
「アヤ!」
と、駆け寄ってきた。
「……姉さま……」
そう呟いて、倒れそうになったところを、舞台に飛び乗ってきたその女性が抱き留めた。
「無理をさせてしまったわね。もう休みなさい、アヤ」
佐保山郁(さおやま かおる)――「北の街」の女王。五大女王の五人目。出演作品は「芸術学院シリーズ 狂おしく虚しく」ほか多数。郁子とは義姉妹の盃を交わしている。
「ですが、まだ二人……」
「大丈夫よ、あとは私たちが引き受けるから」と、続いて舞台に上がってきた女性も言った。「アヤさんは頑張りすぎだよ」
水島有佐(みずしま ありさ)――「北東(うしとら)の街」の女王。五大女王の四人目。出演作品「芸術学院シリーズ」
「五大女王の言うことは聞くものよ、アヤさん」
流田恵莉(ながれだ えり)――「南東(たつみ)の街」の女王。五大女王の三人目。出演作品は「芸術学院シリーズ」「復讐の女神(エリーニュース)になる時」など。
「アヤさんには他にやってもらいたいことがあるの。だから、今は休みなさい」
武神莉菜(たけがみ りな)――「南の街」の女王。五大女王の二人目。出演作品は「夢、それとも幻」
「やってもらいたい……こと?」
郁子が聞くと、最後の女王が答えた。
「私たちは先刻まで御祖の君に呼びかけていたの。お出ましくださいと……でも、駄目だった。私たちは最早、五大女王とは名ばかり。もう、御祖とは心が通じていないのよ」
北野真理子(きたの まりこ)――「東の街」女王。五大女王の筆頭。出演作品は「JUNOシリーズ」
「そんな、東の街さま……」
「現実よ、アヤさん。だけど、あの方なら……御祖の君がいま最も愛されているキャラクターである、あの方なら。御祖を天岩戸(あまのいわと)から連れ出せるかもしれない」
「それは、もしや……」
郁子にも心当たりがあった。自分と同じ片桐家の血筋で、しかも前世は女神であったという設定を持つ……。
「現在執筆中であったにも関わらず、町の周りに一瞬のうちに防御壁を築き、御祖からの影響から逃れた、あの町――私たちは入ることができないけど、あの町の物語に出演していたあなたなら、きっと入れるわ。だから、あの方を連れてきてもらいたいの」
「……分かりました、東の街さま。私に――この北上郁子にお任せください」
その町の名を「神々の御座シリーズ・人間界の町」。町長は、片桐枝実子(かたぎり えみこ)だった。icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/19 18:10:59
icon
突然始めてみました。
誕生日記念に短編を一つ書いとこうと思ったのですが、今日中に終わらせるつもりが、ちょっと無理みたいです。
何日かに分けて書こうと思います。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/19 18:09:03
icon
ようこそ!BFWへ・1
北上郁子(きたがみ あやこ)はいつも通り薙刀の稽古をしていた。
「乾殿(いぬいどの)」と呼ばれる郁子の屋敷には剣術を稽古するための道場も、ピアノ専用の部屋も備わっている。この世界を統治している《御祖の君(みおやのきみ)》からご寵愛をいただく町長(まちおさ)の一人ともなれば、それなりの暮らしは約束されていた。だからと言って驕り高ぶらないのが郁子の良いところであった。
そんな郁子の所に、慌ただしく廊下を走ってやって来た者がいた。
「町長(まちおさ)! 阿修羅王(アスーラ)様!」
阿修羅王というのは、郁子が物語の中で名乗っている二つ名である。「芸術学院シリーズ」の登場人物・北上郁子は、学生時代に文学の勉強をしながら、大梵天道場というところで武術を習い、師範代の一人である阿修羅王を襲名している――という設定である。
『私をこの名で呼ぶということは……』
郁子は薙刀を振り下ろすと、右手に持って待っていた。
慌ただしい人物は、道場のドアを開くと言った。
「町長! 大変でございます!」
入ってきたのは、大梵天道場で郁子の後輩にあたり、師範代の一人・夜叉王(ヤクサー)を襲名している神原晶(かみはら あきら)だった。
「何事です、神原。騒々しい」
「みおやが! 《御祖の君》がお籠りになられてしまわれたと、今、居城でご奉公中の今井殿より知らせが!」
「御祖が?」
御祖が籠る――どこか具合が悪くて私室から出て来ないのか、それとも何か精神にダメージを受けて、心を閉ざしてしまったのか。
『御母君が亡くなられたときは、三日ぐらい放心状態だったけど……まさか』
郁子は薙刀を目の前に翳して、両手に持った――右手は逆手で。
「散(さん)!」
郁子が薙刀に言霊をかけると、薙刀は阿修羅神が彫られた中央から真っ二つに割れた。そして、両手に分かれた薙刀をぶつけ合わせて、くの字に曲げ、スカートの下に隠しているホルダーに、右手のを左足に、左手のを右足にはめ込んだ。
「参ります……」
郁子は神原を連れて通信室へと向かった。そこにはすでに、夫の高木祥(たかぎ しょう。この世界では夫婦別姓が多い)と、秘書官の梶浦瑛彦(かじうら あきひこ)がいた。
「待たせたわね、ショオ。梶浦」
「僕は待っていないよ。それより、洋子君が」
「アヤ先輩!」
通信機のモニターから、今井洋子(いまい ひろこ)が呼んでいた。
「大変なんですゥ! 御祖が引き籠ってしまって、全然反応がないんです!」
「具合がお悪いの?」と郁子は聞いた。「それとも……」
「病気とかではないみたいです。窓から覗いてみたら、ただ部屋の中でお座りになってるだけで」
「あえて言うなら、心の病ね、きっと……そうなると……」
《御祖の君》が重病などで執筆活動が出来なくなると、この世界の住民の中で、現在執筆中の作品の登場人物たちに影響が出ることがある。
「どこか影響が出てる町はない?」
「あります! 〈神々の御座シリーズ・人間界の町〉は、通信に障害電波が出ていて、ほとんど会話ができません。〈雪原の桜花の町〉は完全に通信が途絶えています」
「障害電波ではなく、完全に途絶えているの?」
「はい、完全に無反応です」
「すぐに〈雪原の桜花の町〉に誰か向かわせて! 住民たちが危ないわ。〈神々〜〉は大丈夫でしょう。……私もそちらに行きます」
「お願いします! お待ちしてます」
郁子は通信を切ると、祥に言った。
「あなた、また一緒に舞ってくれる?」
すると祥は郁子の両手を取った。
「君と舞えるのなら、どんな時でも大歓迎だよ。でもその前に、君はその汗を落とした方がいいんじゃないかな?」
薙刀の稽古をしていたので、体中に汗が噴き出していた。だが、
「時間がないわ。シャワーなんて浴びてる暇はないの」
「そう」と、祥は言って、神原の方を向いた。「お湯で濡らしたタオルを持ってきてくれ、部屋まで」
「かしこまりました」
神原は答えると、すぐに通信室を出て行った。
この世界――Bellers Formation Worldは、御祖の君と呼ばれる淮莉須 部琉が作り上げた想像と創造の世界である。この世界で起こるすべての事象は、御祖の意志と夢が影響していた。
その御祖が心を閉ざして引き籠り、その結果、一つの町が消えようとしていた。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 5
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/17 11:50:46
icon
「夢のまたユメ・46」
長峰家の居間は和室だった。宝生家も居間兼仏間は和室だから、正座には慣れているが……長峰家の大物二人を目の前にすると、緊張がなかなか解けない。
そんな百合香を和らげてくれたのは……。
『あっ、この香り……』
翔太の母の真珠美がティーセットを運んできた。そのティーポットから百合香が一番好きな紅茶の匂いが香ってきたのだ。
「おっ?」と勝幸が言った。「いい匂いだね、母さん」
「百合香さんから今日いただいた紅茶よ。なんて銘柄だったかしら? 百合香さん」
「はい。ルピシアのネプチューンです」
「ほう……」と勝基も頷いて、自分の前に差し出されたティーカップを手に取った。「蜂蜜を入れてみたのか? 真珠美さん」
「入れたんじゃないんですよ、お父さん。茶葉に初めから練りこまれているんです」
「ほう、それは面白い」
「だから砂糖なんか入れなくても、ほんのり甘いんだよ」と翔太が言った。「父さん、入れないで飲んでくれって」
「おっ、そうか」
勝幸がシュガーを入れようとしていたが、翔太の言葉でやめて、一口飲んでみた。
「ああ、うまい……美味しいですよ、百合香さん」
そう言われて、百合香は恐縮しながらも笑顔でお辞儀をした。
「うん、うまいなァ」と勝基も言った。「百合香さんは紅茶がお好きなのかな」
「はい、大好きです」
「他にはどんなお茶を?」
「中国茶なども好きです。ノンカフェインのハーブティーなども飲みますが……」
「緑茶は?」
「緑茶はあまり……ほうじ茶は飲むのですが」
「茶色いお茶がお好きなんですな」と勝基は笑った。「ではお酒は?」
「お酒はまったく……」
「飲まないのかい?」
「はい、飲めないんです。飲むと喉が焼ける感じがして」
「リ……百合香は」と翔太は言った。「喉がデリケートに出来てるんだ」
「そうなのォ」と真珠美が言った。「だからそんなに綺麗な声なのね」
真珠美はそう言いながら、勝幸の隣に座った。
「百合香さんには他にもいろんなお紅茶をいただいたのよ。みんな、とってもいい香りなの。きっと美味しいと思うわ」
真珠美が言うと、勝幸が言った。
「趣味がいいんですね。洗練されているというか……小説をお書きになられるのですよね」
『あっ、来た……』と百合香は思った。当然聞かれる質問だとは思っていたが、どのタイミングで来るのかドキドキしていたのだ。
「はい、ネット小説を少々……」
と百合香が答えると、勝基が言った。
「いやいや、ご謙遜を」
そして和服の懐から、百合香が唯一出版した新書版の本を出した。
「読ませてもらいましたよ。なかなか良い……若者向けには」
「あっはい……私のはライトノベルですので」
「そうですな。わしとは感覚が合わないのは仕方がない」と勝基はニヤッと笑った。
『まずい、気を悪くされたかしら?』
と百合香が心配していると、テーブルの下に隠れて、横から翔太が百合香の左手をポンポンッと叩いた。
『あの程度なら大丈夫だよ』と言っているようだった。
「でも百合香さんの文章は読みやすいですよ」と勝幸が言った。「そもそも正しい日本語を使っている。若い人特有なおかしな日本語を使っていないから、我々でも共感の持てる文章だった。それに、古典文学を良く勉強しておられるようだ。ネットに掲載していた、平安時代を舞台にした、帝の女御だったのに帝が崩御したので実家に帰ってきて、若い公達(きんだち)に恋してしまう女性の……」
「“冬の散華”ですか? 読んで下さったのですか!?」
二年ほど前の作品である。そこまでネット掲示板を遡って見ているとは思っていなかった。
「あの当時の女性は、男性とは距離を置かなければならなかった。慎み深くしていることが当たりの前の世の中で、しかも帝の女御だった自分が、十歳も年下の公達に恋してしまった苦悩と、切なさ。良かったですねェ。源氏物語の六条の御息所を思わせますが、しかしそれとは違って、自分から儚く消えることを選んでしまう。それを知った公達が若さと情熱で追いかけていく……いや、実に良かったですよ。あれはライトノベルではなく純文学としても通用しますよ」
「……ありがとうございます」
そんなに評価されるとは思わなかったので、百合香は嬉しくも恐縮した――恐縮してばかりで、コロボックルのような小人になりそうな幻想が浮かんできた。
「あら、そんなに素敵なの?」
と真珠美が勝幸に聞くと、
「おまえも後で読んでご覧、プリントアウトしてあるから。お前好みの作品だよ」
「ええ、貸してちょうだい」
家政婦が部屋の外から声を掛けてきたのは、そんな時だった。
「お嬢様がお戻りになられました」
「やっと来たか」と勝幸は言った。「紗智子にもここに来るように言いなさい」
「かしこまりました」
すると、
「もう来てるわよ」と引き戸を開けて入ってきた人物がいた……百合香と同じくらいの長髪で、スラッと背の高いグラマラスな女性。真珠美に似ているが、母親よりずっと美人だった。
翔太の姉・長峰紗智子(ながみね さちこ)はついこの間二十八歳になったばかりだった。その彼女が百合香を見た途端、駆け寄ってきて、しゃがんで百合香の顔を掴んだ。
「あなた本当に四十歳!?」
「あっあの……三十九歳です、まだ」
「姉ちゃん! リリィに乱暴するなよ!」
翔太が姉を引き離そうとすると、
「だって! 全然アラフォーに見えないんですもの! 私と同い年――いや、年下に見える!」
「そ、そんな、言い過ぎです」
「言い過ぎじゃない! なに、このすべすべで白い肌。ノーメイクなのに!」
「え?」と真珠美が驚いた。「お化粧してないの?」
「そうよ! ホラ、ファンデ付いてない!」
紗智子は百合香の頬を触っていた掌を真珠美たちに見せた。確かに付いていないし、百合香の頬も化粧崩れを起こしていない。当然である、初めからしていないのだから。
「ほう!」と勝基は感心した。「化粧しないでその若さでしたか。こりゃ驚いた」
「だから俺が言っただろ!」と翔太が言った。「リ……百合香は年齢差を感じさせない女性なんだって。だから、ちょっとぐらい年上でも問題ないって」
「翔太の言うとおりだな」と勝幸は言った。「社交の場で、バランスの取れていない夫婦が並んでいるのは見苦しいが、百合香さんは翔太と並んでも見劣りしない――それどころか似合いの二人だ。それに百合香さんは文学の知識も豊富なようだし、いざとなったらうちの社員として働けるだけの技術も持っている。それだけでも翔太の嫁には申し分ないと言える」
「じゃあ、俺たちの結婚を許してくれる?」
「それはまだ早いわよ」
と、言ったのは紗智子だった。「あなたは高峰書房の将来を担っているのよ。そう簡単に伴侶を決められると思ったら、大間違いなの」
「なんだよ、姉ちゃん。百合香に不満でもあるのかよ」
「彼女自身にはないわ――でも……」
紗智子は百合香の隣に座り直した。
「百合香さん、私ね……今、後学のために、朝日奈印刷に出向しているの」
「……え?」
百合香が勤めていた会社に、いる?
「あなたの話を聞いたわ。どうして、あなたが会社を辞めなければならなかったのか」icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/10 12:41:23
icon
「夢のまたユメ・45」
子供が走り回っている。
「テンソウ!」
と言いながら、おもちゃをガチャガチャ言わせている子もいれば、
「イッピツソウジョウ!」
「イッカンケンジョウ!」
とポーズを取っている子もいる。
「天装戦隊ゴセイジャーVS(たい)シンケンジャー エピックON銀幕」の初日は、予想以上の大賑わいだった。
「まだ仮面ライダーも上映してるからねェ」
パソコンで動員数を確認しながら、ぐっさんが言った。「スーパー戦隊(ゴセイジャーVSシンケンジャーの略称)見た後、ライダー(仮面ライダーの略称)も見ようってお客さんもいるよね、この動員数の多さは」
ちょうど上映時間がスーパー戦隊の上映終了時間の10分後に仮面ライダーがある。最近ちょっと動員数が落ちてきたライダーが、今日になって盛り返してきたのはそういうことなのだろう。
「あっ、転んだ……」
アナウンス担当のユノンが呟く――その視線の先に、転んでポップコーンを落とした子供がいた。子供がお母さんに「ホラ! 気を付けないから!」と怒られて、泣き出している。
「ナミ」とぐっさんは、ちょうど通りかかったナミを捕まえた。「あれ、なんとかしてきて」
「ああ、ハ〜イ」
『リリィさんがいなくても、俺って使いっパなんだなァ……』
ナミはそう思いながら箒を手にしたが、ぐっさんにしてみれば(百合香にとってもだが)、すぐに動ける人間の方が戦力だから頼むのである。
『今頃リリィさんはどうしてるのかなァ……』
百合香はその頃、翔太の家――長峰家に来ていた。
門から玄関までが遠い……こんな家、百合香の周りには誰もいない。それだけでなく、もう家自体が大きい。
『お、お金持ち……』
百合香は気が遠くなりそうだった。まさに、\(゜ロ\)ココハドコ? (/ロ゜)/アタシハダアレ? 状態だった。
『ええっと……出版社ってそんなに儲かるんだったっけ? まあ、ピンキリだけど……。私が契約している出版社とは大違いってこと……あっ、いかんいかん!』
百合香はついつい貧乏人丸出しの考えを巡らせてしまった。
「リリィ、何してるの?」
百合香が呆然と立ち尽くしているので、翔太が声を掛けた。
「寒いから、早く入ろう。みんな待ってるから」
「あっ、うん……」
百合香の家――宝生家は、歴史をたどれば古い家柄だが、現代はしがない一般家庭。そんな自分が、こんな立派な家の跡取り息子と結婚なんて、本当にしてもいいのか、かなり不安になってきた。
百合香が家の中に入ると、最初に出てきたのは翔太の母だった。
「まあ、いらっしゃい! 待ってたのよォ」
以前電話で話した時とまったく同じテンションだった。本当に、息子の恋人が遊びに来てくれたのが嬉しい、というのが素直に伝わってくる。
翔太の母・長峰真珠美(ながみね ますみ)、四十八歳――この家では一番百合香と年が近いことになる。
「さあ、上がって。生憎、お父さんがまだ長電話中で、しばらく本など読みながら待ってていただける?」
そう言って通されたのは、一部屋すべて本棚――いわゆる書庫だった。そこに分厚い本から、普通の文庫本まで、文学書と名のつくものはありとあらゆる物が並んでいた。
「すごい……もしかして、夏目漱石全部そろってる?」
百合香が翔太に聞くと、
「そろってるよ」と翔太は自慢げに微笑んだ。「あと、井上靖と芥川龍之介と……リリィが好きなのは誰?」
「萩原葉子!」
「娘の方なんだ、父親の萩原朔太郎じゃなくて……」
「私は詩よりも小説だから」
「なるほどね……ああ、あった」
翔太はハ行で並んでいる本棚へ百合香を連れて行った。
「ほら、ここに父親と一緒に並んでる」
「すごい、私がまだ持ってないのもある……」
「貸してあげようか? 祖父さんのだけど」
「そんな!? 恐れ多い……」
百合香は顔の前で両手を振って断ると、その時に、背表紙がすべて統一された本棚があることに気が付いた――しかも、見覚えがある。
「あれ、全部同じ出版社?」
百合香が指さすので、翔太も振り向いた。
「ああ、あれね……祖父さんの趣味で作らせたんだ」
「あっ!」
つまり、長峰家が経営する出版社の本。
『え? だって、あの背表紙は……』
百合香は近づいて、一冊の本を手に取った。
奥付を開いて見る――想像した通り、印刷所は百合香が以前勤めていた会社・朝日奈印刷(あさひないんさつ)だった。そして、出版社の名前は……。
『秀峰書房(しゅうほうしょぼう)! 業界最大手じゃない!』
百合香がまたしても立ち尽くしていると、そこに翔太の父親と祖父が入ってきた。
「お待たせしたね、百合香さん。ちょうど、仕事の電話が入ったもので……」
その顔に、見覚えがあった。取引先の社長として、朝日奈印刷の重役たちが案内しながら、印刷現場を視察に来た。その時、機械校正担当だった百合香も声を掛けられたのである。
「ああ……やっぱりあなただ。覚えてますよ。勘のいい校正士さんだったのでね」
秀峰書房社長・長峰勝幸(ながみね かつゆき)――もう六年も前のことなのに、ちゃんと百合香を覚えていた。
「ご無沙汰を、致しております」
百合香は緊張しながらお辞儀をした。
「わしも噂は聞いておりました」と言ったのは、翔太の祖父であり秀峰書房会長の長峰勝基(ながみね かつもと)だった。「あなたがミスを見つけてくれたおかげで、我が社の一〇〇年史が刷り直しにならずに済んだそうですな」
「いえ、そんな……」
恐縮しながらも、百合香は思い出していた。そういえば、秀峰書房の一〇〇年史を印刷することになった時、原稿では創始者(翔太の曽祖父)の名前に赤字で訂正が入っていたのに、直っていないことに気付いた百合香が印刷機を止めるように指示を出して、事なきを得たのだった。
『確か、勝眞(かつまさ)の“眞”の字が、新字体“真”になってしまっていたから、旧字体の“眞”に直すように赤字が入っていたのに、直っていなかったのよね』
実は、印刷所ではよくあるミスなのである。何種類ものパソコンでデータをやり取りするので、互換性が完璧でないと、新字体が旧字体に、またその逆に変化してしまう、通称「文字化け」という現象が起こることがあるのである。
「へえ!」と翔太は驚いた。「あれって、リリィが見つけたんだ! 初めて知った」
「私も、あなたが高峰書房の人だなんて知らなかったから……」
「まあ、ここではなんですから」と勝幸は言った。「居間の方へどうぞ、百合香さん」
「はい……」
勝幸が案内してくれようとしていたので、ますます恐縮した百合香だった。icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/03 12:06:46
icon
「夢のまたユメ・44」 数日後。 翔太が勤務している会社――正確に言うと翔太の父親が経営している出版社では、会議が行われていた。 それまで文学書は純文学しか扱っていなかったその会社では、最近の傾向を取り入れて、とうとうライトノベルの雑誌を創刊することが決定した。その新しい雑誌の編集部を立ち上げるとともに、創刊号に執筆してもらう作家を誰にするか話し合っていた。 その会議室の末席に翔太も座っていた、営業部の人間として。 執筆者候補の一覧表には、年末秋葉原で会った紅藤沙耶(くどうさや。崇原沙耶の筆名)の名前もあった。後は草薙建(くさなぎ たける)(漫画家タケルノミコトとミヤヅヒメ の、脚本担当のタケルノミコトの方)や、竹林紫衣郁(たけばやし しいか)など、紅藤沙耶と同じ専門学校・芸術学院の卒業生たちが名を連ねていた。 『これって、やっぱり紹介者は北上郁子(きたがみ あやこ)先生なのかなァ……』 と、翔太は思った。紅藤沙耶も草薙建も北上郁子親戚でもあるから。 「他にも執筆を頼みたい作家に心当たりはありませんか?」 編集長になることが内定している社員が言うと、その隣に座っていた社員が言った。 「草薙先生の小説の挿絵は、やっぱりミヤヅヒメ先生に書いてもらうのか?」 「それもいいし……草薙先生はお兄さんもイラストレーターなんだよ」 「草薙大和(くさなぎ やまと)だろ? 知ってる。川村忍先生が良く好んで挿絵を描いてもらってた作家だろ」 「兄妹の共作か……それもいいね」と言ったのは、他の社員だった。 「しかし、紅藤先生も草薙先生も、旦那さんがうちのライバル社である海源書房の社員だろ? 引き受けてもらえるのか?」 「それは大丈夫だと思いますよ。現に草薙先生は海源書房とは縁もゆかりもない雑誌で漫画描いてるわけですし。そこは気にしなくていいと、北上先生が言ってました」 『やっぱり北上先生が絡んでたか(^_^;)』 翔太はこっそりと苦笑いした。すると、 「他にも候補者はいないのか?」と社長の長峰勝幸(ながみね かつゆき)は言った。「イラストレーターではなく、小説家の方だ」 「ライトノベルを読んでいる社員からもアンケートを取って、この先生方を選出したのですが」 「ふうん……長峰君は?」 勝幸の言葉に誰もが黙る中、かなり間を置いて、 「え?」と翔太が返事をした。 「営業部の長峰君。君ならライトノベルもかなり読んでるだろう。ネット小説なども」 「……」 百合香の名前を言わせようとしているのか? と勘繰ったが、翔太はそこには触れずに、こう言った。 「紅藤先生には直接お会いしたことがあります。あの先生は交友関係も広いようですから、先生に紹介していただくというのは如何でしょうか」 「ほう……」 息子の切り返しに多少感心していると、編集長が翔太に言った。 「え? 紅藤先生に会ったことあるの?」 「はい。年末に友人と行ったところで、偶然お会いしまして。ご主人と一緒にいらっしゃって」 「崇原さんにも会ったのか!?」 「はい、名刺も交換させていただきました」 「それは都合がいい。じゃあ、紅藤先生に交渉に行く時は、君も同行してもらおうかな」 「あっ、はい。是非!」 それからしばらくして会議が終わり、皆が会議室から出ようとしているところを、翔太は父親に呼び止められた。 「ちょっと来い」 「……はい、社長」 皆が出て行ってから、勝幸は言った。 「おまえの彼女は推薦しなくていいのか?」 「やっぱり、俺のこと試したな? 父さん」 二人だけになったので、翔太は息子の顔に戻った。 「書いてるんだろ? 書籍も出してるって聞いたが」 「書いてるけど……俺が推薦したら、完全にコネになるじゃないか」 「それが嫌なのか。おまえの彼女も、自分の作品をおまえに売り込ませようとはしないのか?」 「リリィはそんな女じゃないよ! 第一、彼女は俺の父親がどこの出版社の社長なのか、一度も聞いたことがない」 「そうか……勘繰って悪かったな。週末、会わせてくれるんだろ? 母さんから聞いたぞ」 「ああ。わざわざ、仕事休んでもらったんだ」 「そうか。会うのが楽しみだな」 勝幸は翔太の肩をポンポンッと叩いてから、会議室を出て行った。 『やっぱり、そうゆう風に思われるんだよな。歳の離れた女が、まだ若い男と結婚しようとするのは、なにか裏があるんじゃないかって』 百合香からメールが届いたのは、ちょうどそんな時だった。 《明日お休みだから、今日は遅くまで外出しても大丈夫なの。翔太は?》 翔太はすぐに返事を書いた。 《今日は早く帰れるから、どっか食事にでも行こうか?》 すると返事はすぐに戻ってきた。 《じゃあ、駅前で待ち合わせましょ》 翔太は、楽しいはずの百合香とのメールのやりとりが、今は少し辛く思えた。 百合香と会って、食事だけで済むわけがない。 しかし今日は百合香の自宅ではないから、あまり長い時間一緒にはいられない。 けれど、 『誰にも聞かれてない安心感から、いい声出すこと(^。^)』 百合香の美声を独り占めできるのも、翔太の幸せの一つだった。 十分に百合香で満喫した後は……百合香を眠らせないようにするので必死になった。 「リリィ、起きろ! お兄さんが帰ってくる前に帰るんだろ!」 「う……うん」 最近仕事量が増えたせいか、家でもうたた寝をしてしまうことが増えた百合香は、翔太との営みの後が一番眠いようだった。 それでもなんとか洗顔で目を覚ました百合香は、 「お待たせ」と愛らしい笑顔で翔太の腕に絡まってきた。「家まで送ってくれるんでしょ?」 「うん、夜道は一人じゃ怖いんだろ? ちゃんと送るよ」 二人はタクシーで百合香の家に向かった。 車中で、翔太は近いうちに紅藤沙耶と会うことになったことを話した。 「へェ〜、沙耶さんが翔太の会社で書くんだァ」 「まだ分からないけど、なんとか承諾してもらえるように頑張るよ」 「頑張って。その雑誌できたら、私も買うね」 「あげるよ、もらえるから。……なあ、リリィ」 「ん〜?」 「リリィも、書きたい? その雑誌で……」 「う〜ん……」 百合香は背もたれに更にもたれながら、考えた。 「それってつまり、あなたのコネでってことでしょ? 嫌よ。それは私の実力じゃないもの。私は実力で勝負して、認められて、本を出したいの。認められもしないのに、形にしたって、みっともないだけよ」 「うん……リリィならそう言うと思った」 早く家族に会わせたい――と、翔太は思っていた。そうすれば、百合香がどんな人なのか、ちゃんと理解してもらえる。自分にとってどんなに大事な人なのかも。 『そうして、誰もが納得してから、俺がリリィの小説を出版するんだ! 今はしがない営業マンだけど、いずれは編集部に移って……』 翔太の野望が膨らみつつあるのを、今は誰も止められなかった。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: エリスさん
2012/02/02 21:24:13