サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: ぽっぽさん
2020年09月16日 05時47分54秒
icon
コロナ大恐慌25!
皆さん、おはようございます\(^_^)/
今朝は午前4時前頃からもう目が覚めてしまいましたので、お隣の奥さんから頂く新聞記事が6枚溜まりましたので、3枚分を「コロナ大恐慌25!」として作成しました。
【コロナ大恐慌25!】 8月下旬~9月上旬の新聞記事からです。
例によりまして、お隣奥さんからの新聞記事です。
8月末から今月初旬の3枚分です。
(残りの3枚分は次回に・・・)
今回もずいぶん長くなってしまいましたが、お許しを・・・
例によりまして「くどい文章」ですので、私が付けました「太文字」だけでも目をとおしていただければ・・・と思います。
いつものごとく「<~ ~>」は私が挿入しました o(^-^)o
【政治と科学】 真山 仁氏(まやま じん:作家)
長い記事ですので、目に止まったものだけをピックアップします。
= 感染症対策は安全保障 無自覚な日本 ~公衆衛生~ =
<新型コロナウイルス蔓延が深刻化の中話題になった映画「コンテイジョン(接触感染:2011年発表)」を紹介しているが省略しますね>
・2006年、インドネシアでは「鳥インフルエンザ(H5N1型)」が人から人に感染する事態が起き死者がでた。
それを受けてNHKは2008年1月に危機を喚起するNHKスペシャルを2夜連続で放送した。
だが、日本政府は万全の体制で新型インフルエンザ対策を行っていなかったことが2009年に暴露される。
・また、同年<2009>4月、北米を中心に新型インフルエンザが発生、半年間で約40万人が感染し約4千人が死亡した。
このインフルエンザは警戒されていた鳥インフルエンザではなく、「豚インフルエンザウイルス(H1N1型)」で低病原性だったにもかかわらず、世界はパニックになった。
・日本でも同年5月にカナダからの帰国高校生の感染が確認され、最終的に約2千万人が感染、200余名が亡くなった。
完全な治療薬もワクチンもなかったので政府は対応に追われたが、当初予想された感染爆発には至らなかった。
そのため大騒ぎしたことが批判されたが、それが未知のウイルス発生に対する警鐘の軽視へとつながったのだろうか。
・なぜこんな愚考が続いたのか、それは国民の命の安全を守る公衆衛生を安全保障として考えてこなかったからではないか。
= 専門性高い官僚を 記録残せ =
・厚労省で医系技官の経験もある「高橋謙造(提供大学院公衆衛生研究科教授)」は「いつ起きるか分からない危機について、役所の対応は及び腰だ」と話す。
今年1月24日、「新型コロナウイルスは無症状でも感染する」と香港の研究者が発表しているが、日本政府の反応は鈍かった。
この段階で、日本政府は中国からの渡航を全て禁止する措置を断行すべきだった。
だが、震源地と言われる武漢市がある湖北省からの外国人客の渡航を拒否したのは1月31日だった。
高橋氏も「公衆衛生は安全保障という考えに賛同するがそのような考え方は厚労省内では多くない」と嘆く。
・厚労省には医師免許を有する医系技官がいるが、省内では「専門家よりゼネラリストたれ」という文化があり、専門知識が予防に生かしきれなかったという声がある。
この矛盾こそ、厚労省を含めた「霞が関」の自己矛盾がある。
専門家を集めてセンシティブな事を発発言させるが、官邸はそれを都合よくつまみ食いするだけ。 安倍晋三は責任を取るつもりがなさそうだ。
<どうも「厚労省がネック」ですねぇ! メスを入れる必要がありませんか?>
・公衆衛生とは医療界と政府、更には社会を巻き込んだ、「バイオポリティクス<生物政治学>」と呼ばれる高度に政治的なものだと私は考えている。
だからこそ、厚労省には高い専門知識を有した官僚が必要だ。
だが、安部政権が選んだのは、バイオポリティクス的には「何もしない」という敵前逃亡だったと思えてならない。
「今回のコロナ禍の中で、政府や医療関係者がどのような手立てを打ち、結果はどうだったのかを克明に記録すべきだ」と言う高橋氏の指摘には私も同感だ。
<私も日頃から安倍政権を「敵前逃亡」と思っております。
前にも書きましたが「三現(現場・現状・現実)」を自分の目で見に行かない「腰抜け」だと思っております。
当然「首相の資格」どころか「人間としての資質」に欠けます。 ← 人間失格!
9月に突然辞任したのも敵前逃亡だと思います、全く無責任!。
都合が悪くなると病気のせいにする・・・病気持ちならば首相になるな! 夫婦そろって・・・ダメ夫婦!>
・メディアの使命が「権力の監視」であるとするならば広い視野で、コロナ禍で起きている出来事を正確に記録すべきだ。
政府批判だけでは国民の命は守れない。
<まったくその通りだと思います。 メディアはその「使命(真実を伝える)」を忘れていませんか?>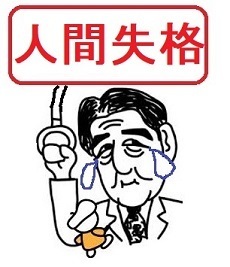
【不確実性と向き合う】 小林傳司氏(こばやしただし:大阪大名誉教授)
= データや知見不足 誤りから学ぶ科学 受け入れる社会を =
コロナ禍で科学は危機打開の欠かせない手立て、データを集めて未知のウイルスや感染解明に挑む科学と、その成果を対策に生かす政治や受け止める社会に間から「不協和音」が聞こえてくる、どう対策すべきかを小林教授に聞く。
▲新型コロナウイルスを「正しく恐れよ」と言われるが、何が「正しい」のか?▼
・「正しく恐れる」は、東京電力福島第一原発事故の後、被曝(ひばく)の健康影響をめぐって使われた。
コロナ禍で直面しているのは、正解が分からない中でどう対処すべきかという問題だ。
科学には不確実性がつきもの、ウイルスの性質や病態は当初から、データや知見が少なくてわからないことばかりだった。
・この半年<インタビューは8月末>、我々が目にしてきたのは、学校で教わる理科のように常に正解がある固定的なイメージの科学ではなく、誤りに学びながら進むダイナミックな科学の姿だ。
・科学者の助言には常に不確実性が伴い、変更を迫られる可能性が高い。
そんな科学観が社会や政治に伝わらないのは深刻な問題だ。
科学が常に正解を出せるはずだと考えるのは一種の「信仰」のようなもの。
▲政府の専門家会議は政策提言や資産を積極的に公表したが、6月の報告書で「前のめりになった」と反省したが?▼
・当初の専門家会議は、法的位置づけは宙に浮いていたが、使命感があり、危機感が政治にうまくつながっていないことを懸念し、思い余って自ら会見し、提言を次々に公表した。
報告書では「専門家会議が政策を決定しているような印象を与えていた」と総括しているが、これは本来政治の問題だ。 彼ら<専門家委員>が追い込まれるほどに政府の対応がうまくいっていなかったのだと思う。
<「報告書」とありますがメディアに公開されたのでしょうかねぇ? 私は「記録は取ってない」と聞きましたが?>
・コロナ対策の中心は医学や公衆衛生の専門家だ。
「人命を救う、疾病を予防する」といった明確な目的を持つ学問だ。
自然現象を正確に記述するのが目的の物理学などの「純粋科学」とは違い、「政策立案と親和性が高い」。
・政策立案の場合では、専門家にも「価値判断」が求められるが、政治責任を課すべきではない。
政治側が総合的な政治判断をする中で、政治や政策と科学との間に「責任」という概念で「ミシン目」を入れてやる必要がある。
▲政治側はきちんと価値判断を判断できているのか?▼
・最近は専門家の意見を聞く前に、政治家が結論をだしていて、専門家が政治の「お墨付き」に使われているのではないかと感じる。
・専門家会議では委員が科学的で実質的な議論をしていた印象だが、今の分科会は政治の諮問(しもん)に答申するだけ、しかも文案を官僚があらかじめ準備する伝統的な省庁の審議会のようになってしまったのではないかと懸念する。
▲「PCR検査をどこまで拡大すべきか」をめぐって、様々な意見が出されているが?▼
・例えば福島原発のトリチウムの問題でも、仮にそれば人体にほぼ無害だとしても、海に放出すれば地元の漁業がまた「風評被害」を受けかねない。
データを示して大丈夫ですといくら言ってみたところで、人の心を科学でコントロールできるとは限らない。
・科学だけではなく、それ以外の観点も視野に入れた総合的判断を下し、きちんと説明するのは本来、政治の役割のはずだ。
【やりがい搾取の罪】 「エッセンシャリワーカー」についての記事です。
新型コロナ禍で尊敬の対象となった「エッセンシャルワーカー」だが、その現場は低賃金の「やりがい搾取」も目立つ。
献身者たちの利他性を社会はどう生かせばよいか?
= 利用と社会の支え必要 = 三浦かおり氏(介護・保育ユニオン共同代表)
・保育園の「ビジネス化」が進んだ。 国が定めていた委託費の使い道を、事業主がほぼ自由に決められるようになった。
人件費を削減し、株主への配当に回しても違法にならなくなり、職員の低賃金化に拍車がかかった。
・利益優先の経営は介護現場でも見られる。 コロナ禍に対応して電話による安否確認をするだけで「介護報酬に算定」されるようになった。
そこで、コロナで利用者が通所できなくなった施設が、必要のない利用者に対しても職員に執拗(しつよう)に電話をかけさせ、利用者から苦情を受けていた。
・ある保育園では、経営者に環境改善を訴えていた保育士が不当に異動を命ぜられたが、保護者が署名を集め組合と連携して会社や自治体に働きかけた結果、移動の撤回と保育環境の改善を実現させた。
・利益優先の福祉を許さない。 そのために現場の労働者が声を上げ、利用者や社会全体が彼らを支える。 こうした取り組みが、働きやすい環境につながり、社会全体の「利益」にもなる。
<「連合は何をやっているんだ!」と思ってしまいます>
= 呼称が「報酬」 冷淡な日本 = 坂井豊貴氏(さかいとよたか:慶応大学教授)
・長引くコロナ禍で医療機関のみならず、保育園や介護施設などで「高い感染リスク」にさらされながら働く人たちへの社会の敬意や感謝の気持ちが高まっている。
「エッセンシャルワーカー」という呼称は、そうした敬意の表れだ。
そもそも「本質的(エッシェンシャル)ではない」仕事などないと思うが、今回は「本質的」という言葉を使うことで、社会が「リスペクト<敬意を表すこと>」という「金銭ではない報酬」を与えているように感じる。
・たとえAI(人工知能)が普及しても、人が担う「エッセンシャルワーク」とされる仕事の多くは残るでしょう。
その賃金を増やすための一案は、最低賃金を上げることだ。
<やはり「連合」は今回の「コロナ禍」で何をしているのだ!と言いたくなります>
= 「役に立て」 圧力は脈々と = 本田由紀氏(東京大学教授)
・雇う側が「やりがい」を強く意識させることで、働き手が低賃金や長時間労働といった環境に順応してしまう。 私はこの構図を「やりがい搾取」と名付け、2007年の論考で指摘して認知されるようになった。
しかし、10年以上たった今でも労働現場の搾取の構造が改善される傾向はみられない。
コロナ禍で注目されている「エッセンシャルワーカー」はその一類型といえる。
・なぜ仕事量に見合うだけの賃金が払われず、「やりがい」が搾取される構造が続いているのか。
理由の一つが日本人の意識にある「世の中に迷惑をかけてはいけない」や「社会の役に立て」という発想だ。
起源は江戸時代の民衆思想の中にたどれるという研究もある。
戦時中は「お国のために命を捧げろ」として戦争に突き進む圧力になった。
戦後は経済戦争を担う企業への献身が求められた。
<「企業戦士」「豊田商法」が頭をよぎります>
・搾取の背景には、根強い「ジェンダー差別」もある。
育児や介護などケアに関する分野の仕事の多くは女性が担ってきた。
高度なスキルが必要なのに、家庭における「育児や家事の延長」のような烙印(らくいん)が押されてしまった。
労働市場で女性が疎外されてきたため、働く女性は低賃金を受け入れざるを得ないという悪循環もある。
・エッセンシャルワーカーの低賃金は容認できることではなく、その社会的な価値を適切に賃金に反映させるべきだ。
そのためには働く側が労使交渉の場で「ノー」と言い続けることが大切だ。
<やはり「連合」は何やってるんだ!といいたくなりますねぇ~!>
今回はここまでとします。
いつもながら「難しい」ことを書かせていただきましたが、次回も「くどい文章」になるかと思いますが・・・よろしくでございます!-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
コメント: 全0件








