サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: ぽっぽさん
2021/07/22 07:59:15
icon
今日もワンちゃん!\(^_^)/

今日もあまりにも暑いので冒頭に「猛暑見舞い」を追加しました!・・・汗;;汗;;
写真の山は「御岳山(3067m)」、2021年3月17日撮影です)
皆さん、おはようございますo(^◇^)o
BGMはネットラジオで「クラシックギター」を。。。
お耳なんですがァ!
昨夜の午後10時25分頃と30分頃にそれぞれ「ピチッ!」が。。。
10時25分のときは、私がブルーレイのリモコンを所定の場所へ置こうとしまして、ベッドの上で体をひねった時に「ピチッ!」と。。。
(肩こりからかなぁ?)
更に、今朝の午前5時前にも「ピチッ!」がほぼ連続的に3度。
(夜中にも1~2度あったかも? 合計7~8回発生ってとこでしょうか。
その後は「虫の音」が元気でございますゥ~!)
【やはりワンちゃん】 ふーたんはワンちゃんが大好きですヨo(^◇^)o!
ふーたんは今朝の午前5時過ぎに「お腹が空いたよね」と「朝食」をやっていました。
私はワンちゃんの朝食後の3~40分後に散歩に行って参りました。
例によりまして「アタイ! イヤナ!」と・・・
抱っこして少し先で降ろしますと、スタスタと・・・
昨夜よりは距離・時間とも短かったですが、大小は無事こなしましたヨ\(^_^)/
(も~! 大変!
「犬は好きか?嫌いか?」と問われますと私は「あまり好きではないかな」でございます。
ワンちゃんの「まつげ」は、右の写真の如く長いですヨ!
(P.S. ワンちゃんは午後1時過ぎ頃に嫁と下の孫が迎えに来ました。
居なくなると寂しいですねェ~!)
さて、今朝から「シワシワ~」と「クマゼミ」が・・・
(私の「虫の音」も元気ですが・・・)
今日も「スパッ!」と参りましょうネ o(^-^)o
(下の写真は物置西の枯れた「銀木犀(ぎんもくせい)」を掘り起こした後に植えました「南天」ですが芽が大きくなってきましたヨ!)
午後、ワンちゃんを嫁が迎えに来ましたので、2部屋の和室の「ガード(畳の部屋に入らないように合板などで)」を外したり、ふーたんはワンちゃんが寝ていましたシーツなどを外したり・・・
二人とも汗だくになりましたので、シャワーを・・・さっぱりしましたヨo(^◇^)o
シャワーでさっぱりした所で、ふーたんはちょっと仮眠でございます。
私は「2社の新聞記事」をワードで作成していました。
さて、五輪はちょっと横へ置きまして・・・
来年は「沖縄復帰50年」ですネ!
お隣から頂いた新聞記事と我が家が取っています今日の新聞記事からご紹介を・・・
(長くて退屈かもしれませんが、お付き合いを・・・
例によりまして「太文字」「<~>」などは適宜、ぽっぽが)
【沖縄、復帰50年へ】 お隣からの新聞 2021年7月中旬
来年、沖縄の日本復帰50年を迎える、<2021年>5月から「復帰50年へ」の記事掲載を始めた。
社会全体で討論すべき課題や視点とは、これからメディアが向かい合うべきテーマとは、沖縄にとって日本にとって復帰とは。
= 「アリと象」の不条理 自分事として考えて = 森口 豁(かつ)氏(ジャーナリスト)
・復帰後も米軍基地が集中し、いくら沖縄が本土に訴えても変わらない「アリと象」の関係が続いている。
その不条理の責任は日本の一人である自分のあると思い、取材を続けてきた。
・東京出身の森口氏が初めて沖縄に渡ったのは、高校卒業後の1956年3月、沖縄出身の後輩に誘われ、米軍施政下の沖縄の高校や沖縄戦犠牲者の慰霊碑を訪れたが、慰霊碑にはゴミが散乱し、空や道を米軍機や車両が"わがもの顔"で行き交う中、交流した地元高校生は「犬(スパイ)がいるかもしれないが、言いたい。 僕は日本の戻りたい」と訴えた。
「米軍の監視が強く、本土メディアも常駐していない「人的鎖国」の時代で、占領とは何かを知り責任を痛感した。
・1959年から地元の琉球新報の記者として移住したが、同年6月に本島中部の宮森小学校に米軍機が突っ込み、児童ら18人が死亡する事件が起きた。
1961年に日本テレビの通信員にもなったが、米軍による事件事故について「本土メディアの関心は低くニュースにならなかった」
・1965年に佐藤栄作<当時>首相が沖縄を訪れ、本土復帰が現実味をおびると、東京の上司は「沖縄のニュースは何でもくれ」と求めてきた。
復帰後<1972年5月15日>は5月15日の「本土復帰の日」や6月23日の「慰霊の日」などの節目になると本土から取材クルーが集まるようになった。
・1995年の「少女暴行事件」や翌年の「普天間飛行場の返還合意」「普天間飛行場の名護市辺野古への移設に反対する故・翁長雄志知事の誕生」など、大きな事件や政局の度に報道は熱を帯びた。
・ただ、結果的に「点」の沖縄報道が続き、注目が高まっては引く波のような状態が繰り返されていると感じて、沖縄は復帰前から「不条理だ」と訴え続けている。
「点」ではなく「線」で報道しなければ、沖縄の問題を自分事と考える日本人は出てこない。
<私には「点から線、線から面」にならなければだめだという持論があります。
手前味噌ではありますが、まだお城で仕事をしていた頃、私共の市会議員さんが友人を連れて登城しました。
友人が天守へ登って行きましたので、残っています市会議員さんとお話を・・・
市会議員さんが「我が町の観光はどうあるべきでしょうかねぇ?」と聞かれた時、私は「点から線、線から面にしなければ」とお答えしたことがありましたヨ o(^-^)o>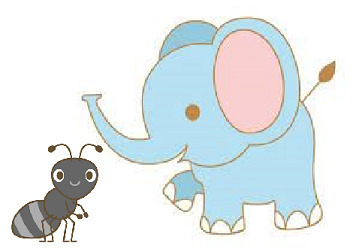
=「復帰」とは―――問う側を映す鏡 = 新城和博氏(地元出版社の編集者)
・「沖縄の日本復帰はなんだったのか?」、この問いは問いかける側を映す鏡のようなものだと思っている。
この30年ほど、度々全国メディアから取材を受けてきたが、何をどう問いかけるかによって、その人が沖縄をどう見て、考えているのかが見えるからだ。
・復帰20年を迎えた1992年、国の記念事業の目玉として「首里城」が復元さえた。
ところが3年後、米兵による少女暴行事件が発生した。
事件を契機に、積み重なっていた米軍由来の事件事故への反発は大きなうねりとあり、翌1996年、日米両政府は「沖縄の基地負担を軽減する」ことに合意する。
代表的なのが、宜野湾市にある米軍普天間飛行場の全面返還の約束だ。
・それからずっと復帰30年、40年が名護市辺野古での基地建設と絡み日本政府対沖縄という構図で語られてきた。
復帰を考える時、入り口は「米軍基地、歴史、文化、観光・・・」なんでもいいし、人それぞれだと思うが、ヒントは「復帰後」からみるということではないか。
<中略>
・<沖縄復帰>半世紀を前にしたいま、本土と沖縄の距離は、かつなないほど近くなったと思う。
沖縄に住む本土の人もたくさんいるし逆もあるが、両者の足元には「溝」があって、近づくほど深くなっていると思う。
米軍普天間飛行場の移設のために沖縄に新たに基地を造るというのは、25年前に日米が約束した「基地負担の軽減」から問題がすり替わっているが、そのことにどれだけの人が気づいているか。
・太平洋戦争末期の沖縄戦で始まった米軍占領が終わったのが1972年5月15日。
来年で復帰から半世紀だが、問われてきたのが過重な基地負担と経済自立だ。
米軍占領下で本土から移された負担も含め、全国の米軍専用施設面積の7割が集中する構図は、復帰2年後にできあがり、変わっていない。
米軍機の騒音被害や米軍由来の事件・事故は絶えず、近年は環境汚染問題も浮上。
・一方、基地関連収入が県民総所得に占める割合は、1965年度30.4%、復帰時15.5%、近年は5%お度に縮小した。
一人当たりの県民所得は全国平均の7割にとどまり、子どもの貧困率は全国の2倍近く。
・経済の柱に成長したのは観光だがコロナ禍が直撃。
2020年度は復帰後最大の減少幅となり、外国時観光客も復帰後初の「ゼロ」だった。
【沖縄 たたかいの足跡】 我が家が取っている新聞 7月22日
= 訪問できぬ今 戦跡ガイド出版 = 大島和典氏(元TVディレクター・平和ガイド)
・沖縄を訪れた小中高生らに「現場で何を感じたか、全てはそこから始まる」と必ず語り、「ただ知っているだけなのか、現場で体験したり話を聞いて感じて得たこととは全然違う。」と語る。
・四国放送(徳島県)退職後の2004年、沖縄県に移住し、沖縄戦を後世に語り継ぐ市民団体「沖縄平和ネットワーク」のメンバーになり、主に修学旅行生らを対象にした平和ガイドを担ってきた。
・「沖縄の海を美しいだけで見ないで欲しい。 目に見えるものだけで判断していたら、人はいつか間違う」
1年前に帰郷(徳島県さぬき市)したが、「沖縄の見方、歩き方の奥義を伝授して欲し」と仲間から誘われた。
「歩く 見る 考える沖縄」は平和ガイド時の原稿をベースに編集、読むとまるで修学旅行のバスに乗って、沖縄の戦跡を巡っている気分になる。
・大島氏の原点は戦争で1945年6月に沖縄戦で父を亡くした。
戦後50年の1995年に沖縄の「平和の礎(いしじ)」の除幕式の特集のために訪れた時、平和の礎に父の名を見つけた時は戦慄した。
・今、コロナ禍で修学旅行の中止が相次ぐ。
例えば「平和祈念資料館」はコロナ前の2019年葉県外から約20万人の小中高生が来館したが、昨年度<2020年>は、1万3千人だけだった。
・平和ネット事務局長・北上田氏は「コロナが収束したら、本当に<修学旅行生が>沖縄に戻ってくるのか心配だ」と明かす。
そんな折の出版に大島氏は「沖縄の地で感じてもらうのが一番だが、今は難しい。 ならば、本を手に何かを感じて欲しい。 知ろうとすることまであきらめないで」と語る。
= サンマ裁判 闘うおばあ 映画化 = 山里孫在(まごあり)氏(沖縄TVプロデューサーで「サンマデモクラシー(ドキュメンタリー映画」の監督)
・沖縄の食卓にサンマが上がるようになったのは戦後からという。
祖国復帰への願いと共に「日本の味」として普及したころ、20%の輸入関税がかけられたが、その根拠となる琉球列島米国民政府の高等弁務官布令にはサンマは挙げられていなかった。
・この事実を知って憤ったのが冷凍サンマを輸入していた魚卸業の「玉城ウシさん」。
1963年に徴収された税金の返還をもとめて琉球政府を訴えた。
当時の高等弁務官は「自治は神話だ」と言い放ち、本土復帰運動を抑え付けた「ポール・キャラウェイ」。
絶対的権力者に立ち向かったウシおばあの戦いは、自治を求める沖縄の人々の巨大なうねりを生んだ。
・復帰に向けた運動の中心は沖縄の教職員組合で、「これから日本に復帰するから標準語を使おう」と先生は言っていた。
復帰は沖縄の人たちの希望だった。
・日の丸を振り、東京五輪の聖火リレーにも熱狂したが、ある時から急速に空気が変わっていった。
沖縄の基地を本土並みに縮小するという願いが実現しないことがわかったからだ。
・「サンマ裁判」を掘り起こしたドキュメンタリー映画「サンマデモクラシー」では、名護市辺野古の米軍進基地建設を巡り、当時の翁長雄志知事が2015年、民意を顧みない当時の「菅義偉官房長官」に向かい「キャラウェイに重なる」といったニュース映像も挿入した。
・山里氏は「沖縄は何度も裏切られ、失望と期待を繰り返しながら民主主義を求めてずっと戦っている島なんだと実感した。 苦味も込みで作品を味わってもらい、50年を経た今を考えてほしい」と話す。
とあります。
今後「沖縄復帰50年」にちなんだ記事を目にすると思います。
気になった記事は適宜ご紹介させていただきますネ o(^-^)o
(下の写真は「ぽっぽ図書館」の沖縄の本です。
右側に図書館の中から「沖縄オバァ列伝」「オバァの喝(カーツ)!」「オジイの逆襲 沖縄オバァ列伝番外編」をアップしましたが、3冊とも面白いですよ。
「沖縄のオバァ」はパワフルでございますヨ!)
沖縄関連の記事のトピックへの追加が終わりましたので、今からふーたんと「久しぶり」にお散歩を・・・
【3日ぶりのお散歩ォ!】 「伊吹山」が奇麗でしたヨ (☆▽☆)
午後5時45分過ぎから、6時半頃までの45分間「ショートコース往復・中池」へ。
脇道から入りますと、相変わらず「ホー・ホケケッ!」と下手な「ウグイス君」は、まだお嫁さんが見つからないようです・・・
(毎年、6月に私たちの先導役をしてくれます「鹿の子蛾」は今年は全然見ませんし、「ハグロトンボ」もあまり見かけません)
下池の堤からと中池の堤からの「伊吹山」です。
昨日のワンちゃんの散歩時と同様に綺麗でしたヨ\(^_^)/
今日パチリしました植物です。
(散歩の所々でもう「紅葉」が!? 「返り咲き」のつつじも・・・
何の実でしょうか、「木蓮(もくれん)」に似ていますが?
グリーンベルトの北端では「ペパーミントの花」が。。。)
さて、ふーたんは「夕食」を用意してくれましたので・・・
皆さん!
また明日でございます。
コメント: 全0件








