サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: ぽっぽさん
2023/08/07 16:55:04
icon
午後からはショッピングぅ~! 歯科医院ン~!
皆さん、こんにちはァ~!
「きなこさん」が、たんぽぽに参加してくれましたヨ!\(^_^)/
「きなこさん」といえば・・・思いだされる方もお見えでは?
そうです、私が月一で通っております「歯科医院」の「歯科技工士さん」でございます。
きなこさん歓迎の花は「百合(ゆり)」です。
(「なぜ、宮古島の百合?」・・・後述です)
さて、台風6号の影響でしょうか、朝からお天気が不順でございまして、午前中にザーッとにわか雨が・・・フッ!
【午後からはショッピングぅ~! 歯科医院ン~!】
今日は午後2時半から私が「歯科医院予約」でございますので、その時間に合わせましてふーたんは「ショッピング」でございますゥ~!
自宅を午後1時40分過ぎに出まして、まずはふーたんを「ホームセンター併設大型スーパー(水泳教室の帰りに参ります)」で降ろしまして、ソノマンマ10分弱走りますと私が通っております「歯科医院」でございます。
(歯科医院には午後2時過ぎと早く到着しましたヨ! でも、もうお二人がお待ちでしたァ~!)
名前を呼ばれるまではお隣から頂いた新聞記事を見ていました。
いつもの「きなこさん」が私の名前を呼んでくれましたので診察用の椅子に・・・
きなこさん:(たんぽぽに)参加しましたヨ!
ぽっぽ :(その場で、スマホ確認しまして)了解いたしました!
きなこさん:(歯は)グラグラしてはいますが、2年前とあまり変わりませんのでマー
マーですヨ!\(^_^)/
やがて先生の診療でございます。
先 生:(いつもの)左端(の歯)に加えて右端(の歯)も少しグラグラしています
が、マー大丈夫でしょう!
ぽっぽ:ありがとうございました。
ってことで診療は終了でございました。
がァ~!・・・
残念ながら「きなこさん」は8月末でこの歯科医院を退職しまして、10月からは「沖縄石垣島」へ、その前に「宮古島」へ行くそうです。
(ですから、上記のごとく歓迎のお花に「宮古島の百合」も加えましたヨ!\(^_^)/
ふーたんは「石垣島へ行くきっかけになる」と。。。)
歯科医院を出まして、ふーたんが待っています大型スーパーへ。。。
(ふーたんは自販機でコーヒーを買って来てくれましたが、少々「濃い」のでやむを得ず「水」で薄めましたァ~!
下の左写真はホームセンターのペットコーナーでのパチリで、右はスーパー側の食料品売り場でして「矢印」はふーたん o(^-^)o)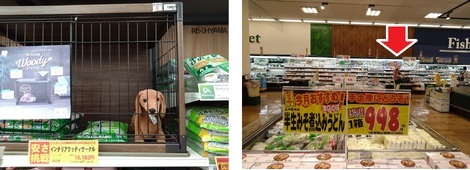
ショッピングの後は真っすぐ帰宅しました。
(ベッドに横になりまして「録画の消化」を・・・)
ってことで「録画:相棒スペシャル(2時間番組)」を見ていましたヨ!
【GPT 科学の現場から】 我が家が取っています今月の新聞記事です。
少し難しい記事でしたので、要所だけをサラリとアップしますネ!
= 実験短縮 パッと論文= <GPTは>優秀な研究助手
・「稲垣貴士さん(名古屋大学大学院工学研究科)」の所属する研究室のテーマは、生物学と工学を融合した「バイオメカニクス」。
ヒトの「肝細胞<幹細胞については既に過去のトピックに書きましたネ! 「何にでも変化できる元の細胞」のようなものです>」を培養するため数日に一回、細胞に栄養を供給する「培地」を手作業で交換する。
この交換作業をロボットに行わせるコードの作成にGPTを使った。
・<GPTへ教え込むことは>手取り足取りではなく、まるで研究室の教授が学生に教えさせるために、ざっくり伝えるイメージだったとのこと。
しかしGPTはそんな雑な要求<で>も理解した上で、高い確率で正確なコードを書いてきた。
・<コードを>書かせた回数は17回、<それを>ソフトで検証すると12回分がロボットを要求通りに動かせるコードだったので、稲垣さんは「7割<12/17>という成功率には驚いた」と振り返る。
・<上記の肝細胞の培養に関する論文で紹介した>コードは40~50行で、研究者が自分でコードを書き17回繰り返すには3カ月近くかかる恐れがあるが、GPTは1日で終わらせた。
稲垣さんは「GPTは”優秀な助手”として、研究者の手を煩わす作業を自動化できその結果、研究者は実験結果の解釈や分析に集中できる。」とみる。
・世界で急速に普及する米国発の対話型AI「チャットGPT」のインパクト(影響)は大きく、自治体や企業、学校が活用方法を模索し、負の側面も論議されている。
一方、大学の研究者らは積極的に使いこなし、既に成果が出始めている。
= ワタシと話し合おう = 社会の課題解決
・GPTはインターネット上の膨大な情報を読み込み、単語やその関係性を学んでいる。
その「大規模言語モデル」が、人との自然な対話を可能にしているが、「白松俊教授(名古屋工業大学・知能情報学)」は「GPTが簡単に人を演じられるレベルにまで進化したことに驚いた」という。
<さらに白松教授は>「いずれは人を納得させる結論をAIが考えられるようになる」と見通す。
・既に<白松教授らが開発した>アプリは、架空の登場人物の満足度を数値化する機能を持っている。
メンタル状態を改善するために悩み事をつぐやくと自動で応じたり、市役所に寄せられた市民の声を効率よく分類したり<できる>。
<アプリの>開発の根底に共通するのは、身近な社会の課題を解決するために情報工学を活用する「シビックテック」という考え方だ。
・ただ、白松教授は「あくまでAIはサポート役で、社会の主役は人であってほしい。
社会の課題を探ったり、できることを考えたりするのは、私たち人間のやること」とっ強調する。
= 助け舟 ヒトが出して = 弱いロボット
・「岡田美智男教授(豊橋技術科学大・認知科学)」らが開発したロボットは、「昔々あるところに・・・えっと」と困ったように視線をそらす。
傍らの<岡田>教授が「桃」とささやくと、ロボットは「それそれ」と。。。
人間と<この>弱いロボットを岡田教授は「互いに緩く依存しあう関係」と説明する。
・弱いロボットは人間とテクノロジーの関りを考える材料として、小学校や高校の教科書にも採用されている。
そんな弱いロボとは「対照的」と岡田教授が位置づけるのが、対話型人工知能(AI)「チャットGPT」だ。
・<チャットGPTは>膨大なデータを学習し、利用者の質問に瞬時に答える一方、弱いロボットのように言いよどんだり、可愛らしく助けを求めたりしない。
岡田教授は「<チャットGPTは>自己完結を目指した発話なので、答えを押しつけられような感覚になる。
間違いもたくさん出るはずだが、それを自分の中で把握できていない」と指摘する。
そこで岡田教授の研究室ではGPTをあえて「言葉足らず」に制御した上で、開発した弱いロボットの会話機能に使おうと試みている。
・従来はプログラミング言語による複雑なコードで会話の細かいルールを指示していたが、GPTなら通常の言葉で指示できるため作業効率も良い。
世の中には、生活を便利にする高性能ロボットがあふれている。
一方で「人間も自己完結や高性能が求められ、生きづらさがある。
人間とロボットが弱点を補い合い、強みを引き出して共生する関係を提示したい」と岡田教授はいう。
・・・ということでございました。
しかしでございます!
やはり「弱いロボット」より「高性能・優秀なロボット」の方が効率的ですよね。
その「高性能のロボット(例えばチャットGPT)」に人間が振り回されたり、人間の判断よりロボットの判断を優先する傾向になるのではないでしょうか?
つまり「ロボット天国・人間不在の世の中になってしまうのでは?」と危惧いたします。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
コメント: 全0件








